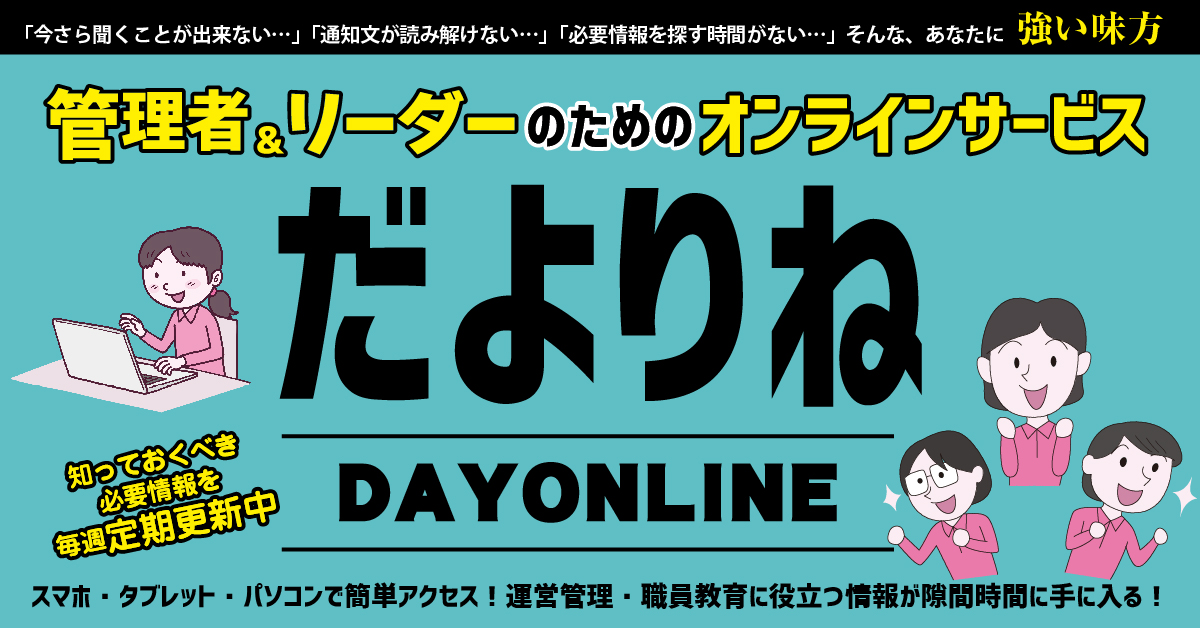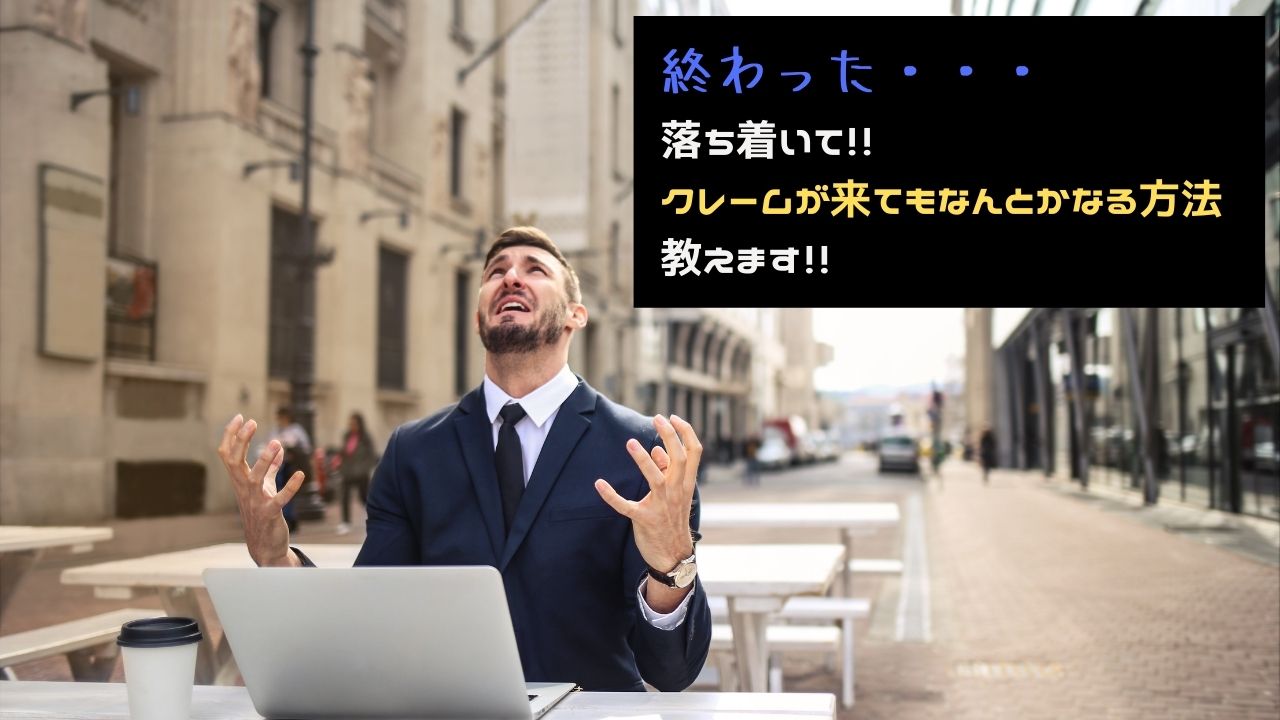【介護保険制度改正・介護報酬改定ミニ講座】これまでの報酬・制度の変化のまとめとこれからのデイ運営
これまでの改定の流れ【通所介護の開設抑制、小規模デイの報酬削減】
平成23年には28,054ヶ所だった通所介護事業所は、4年後の平成27年に42,386ヶ所と約1.5倍に増加しました。
そして、通所介護事業所の急増を抑制すべく、報酬単価の引き下げなども実施されました。
この増加要因の一つが、小規模デイの急増で平成23年に12,725ヶ所だった事業所数は平成28年には23,763ヶ所と約1.9倍になりました。
これを抑制するため平成27年に小規模デイの介護報酬が約10%(通常規模5%)と大幅に削減されました。
さらに、平成30年に新設されたADL維持等加算の算定要件には5時間以上の通所介護費の算定回数が設定され、短時間の小規模デイでは算定不可という加算となりました。
【離職防止A to Z】離職を防ぐために、何から始めるとよいか
スタッフが離職を考えるきっかけ
入社時や異動先に配属になるまで知り得なかったことによるミスマッチが発生することによって始まってしまいます。
(1)業務内容・人間関係のミスマッチ
→予想していた業務と実際の業務が違った
→配属された部署になじまなかった など
(2)賃金・休日などの労働条件
→賃金が低い
→休日も出勤しなくてはならない など
(3)福利厚生・待遇
→福利厚生が不十分
→人事評価が不適切 など
(4)人間関係のトラブルやストレス
→パワハラにあった
→ストレスから体調を崩した など
【利用者を増やす㊙営業術】第14回 誰かが稼働率上昇にブレーキを踏んでいませんか?
稼働率が増えないのは"忙しい"からかも

通所介護の経営を安定させるためには、だいたいどの程度の稼働率が必要が知っていますか?
結論、通常規模型あれば「70%」以上が必要です。

独立行政法人福祉医療機構から出されたリサーチレポートによると
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/190628_No002.pdf
稼働率70%以上でサービス活動増減差額比率が13.8%なのに対し、稼働率が64.1%だと
△11.2%の赤字を計上してしまっていることが分かります。
また、稼働率が黒字事業所より低いのにも関わらず赤字事業所は人件費率が16.9%も高くなってい
ることが表から読み取れると思います。
事業の恒常性を維持するには、「経費支出」に対する必要な「売上」
すなわち「損益分岐売上高」以上の売上を立てるか、売上高に対する経費支出を適正値に落として
利益率を高める必要性が出てきます。
重要なのは「利益率」を上げることです。
ただ、この表を見ていて不可解なのは、同じ通常規模型で「稼働が低い」のにも関わらず
「人件費」が大幅に高くなってしまっている点です。
なぜでしょうか?
大半の理由は「忙しい」から「人を入れて欲しい」
これが原因です。
ここでマネジメントが思考停止すると、売上高が停滞している状態で販管費だけが上がり、利益率が
低下することで、赤字運営に陥ってしまう可能性が高まります。
忙しいのは
・人手不足が直接的な原因なのか?
・オペレーションにボトルネックがあるのか?
・レイバーコストの単価設定が高すぎることによる低配置が原因なのか?
単純な増員の実施だけでなく、思考を凝らし、上記3点については最低限考えたうえで
管理する方が、恒常的な運営はしやすいと思います。
今回の記事では、内側から発生する稼働率停滞への対処法についてお伝えしていきますので
最後まで見て頂き活用頂ければ幸いです。
【利用者を増やす㊙営業術】第13回 ピンチをチャンスに変える逆転のクレーム対応
クレーム対応は至ってシンプルです
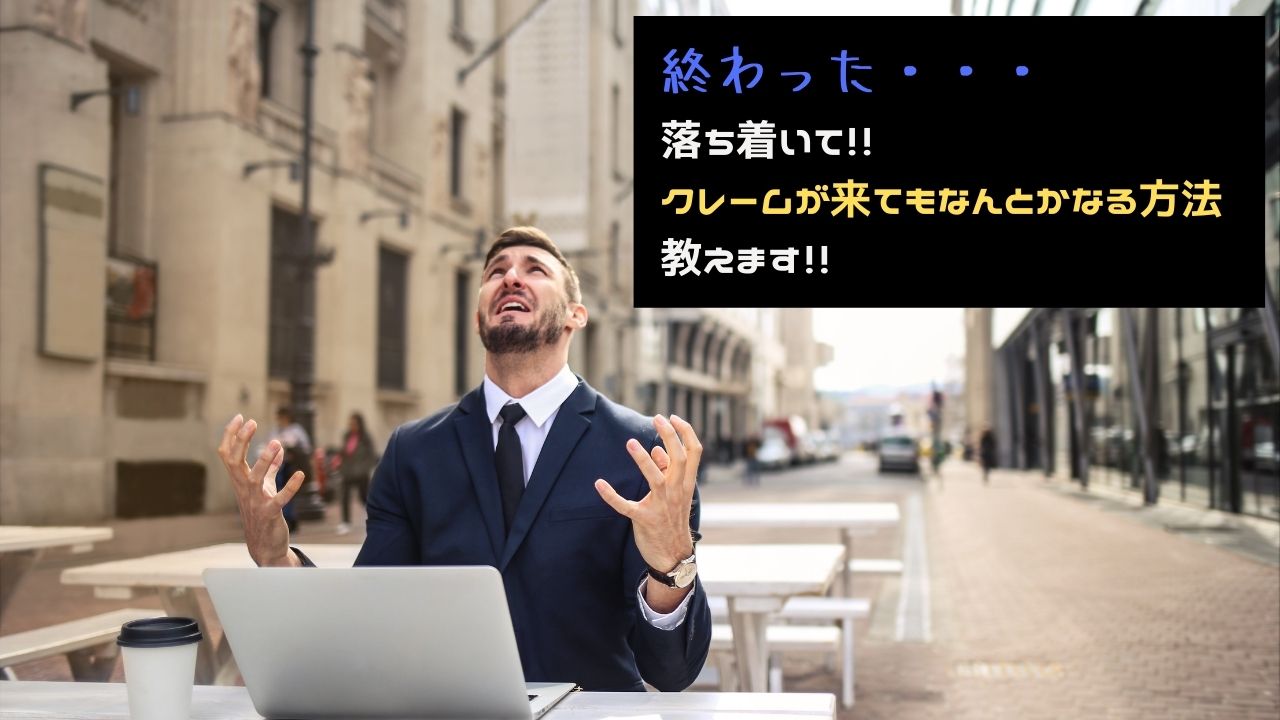
クレーム対応を「この世の終わり」のように思っている人がいますが
その方は「経験不足」か「クレームの本質を知らない方」でしょう。
今回の記事ではクレームを対応を非常にシンプルな視点でひも解いていきます。
実際に私はクレーム対応をいくつも経験しています。
・納期確認ミスで胸ぐらをつかまれ地面に押し倒されたあの日
・メーカーとの連携ミスで土下座したあの日
・事業所内で飼っている犬が道路に飛び出し、何回も謝罪に行ったあの日
・ご利用者との契約内容確認ミスでお叱りを受けたあの日
いやー、思い返すだけで何個あるんだろと自分の未熟さが嫌になりますが・・・
その経験のおかげで伝えられることもあると思うのでそれを今回の記事では紹介します。
ちなみに、全部自分で対応していますので、実践的だと思います。
事例を拾って紹介している専門家ではないので(笑)
まず、クレーム対応で最も重要となってくるのは「導入対応」です。
ここを間違えると全て上手くいきません。ここが「命」です!
次に大切なのが「傾聴と宿題化」です。
聞きなれない言葉だと思いますが、確定要素以外は全て持ち返ります。
いくつ持ち返るか!どう持ち返らせてもらうか!これが重要です。
次に大切なのは、お客様を目の前にしない状況での「分析とお詫びと対策」を決めることです。
この内容によって許して頂けるかどうかが決まります。
最後に大切なのは、「お客様と面会しての謝罪」です。
ここでは、お詫びするべきところはお詫びし、間違っていない部分や相手の責任部分についてはしっかり
追求する必要がありますが、見せ方が非常に重要となります!
これを見るだけで、クレーム対応バッチリできるくらい丁寧かつシンプルに解説をしていきますので、
ぜひ、全て見て頂き活用して頂ければ嬉しいです!
【利用者を増やす㊙営業術】第12回 稼働率が上がらないのは定員枠やサービス種別が適正ではないからかも Part.2
サービス種別ごとに求められているミッションを見誤ると失敗する

介護保険制度ではそれぞれのサービス種別に対してミッション(基本方針)が設けられています!
通所介護であれば、「要介護認定を受けた方が、自宅での生活を続けていけるように、身体機能の維持・向上を目指し、機能訓練をしたり、他者との交流を通して社会的孤立感の解消や認知症予防を図るところです。 また介護者(家族)の身体的・精神的負担の軽減も目的とされています。
通所リハであれば、「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
訪問介護であれば、「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」また、「入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者等が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者等の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話」が目的とされています。
このように、「介護」とは一括りで提供するサービスが決まっている訳ではなく、それぞれの事業種別のミッションに応じたサービスを提供していく必要があり、デイサービスで心身機能の維持・向上だけをしていては基本方針で求められている機能を果たせていないことになるのです。社会的孤立感を解消できているか、介護者の身体的・精神的な負担の軽減もできているかどうか、定量的な評価をして改善状況を伝える必要があるのです。
そもそもの基本方針を果たせていなければ他の事業所に機能面で負けます!
また、各種別ごとに「ビジネスモデル」の基本構造が組み込まれており、それを大きく逸脱する場合も、適正な利益
を維持できない原因となります。
今回の記事では
・各種別ごとの基準・報酬構造をビジネスモデルの基本構造として見る
・事業所のコンセプトと各種別の基本構造の乖離を無くす
という観点から、稼働率や営業利益を高めるためのメソッドをお伝えしていきますので
ぜひ、参考にして頂き活用して頂ければ嬉しいです。
【離職防止A to Z】辞めたい話が出た時に知っておくとよいこと
『あの…ちょっとお話したいことがあるんですけどいいですか?』
「そうやって相談に来られる度にドキドキするんですよね。辞めるの考え直してもらえるように話せるかな…って。でもね、そうやって言いに来てくれた時って、もう心が決まってて、引き止めても無理なケースがほとんどなんですよね。そういう時に自分のふがいなさを感じます。」
こう話してくれたのはデイサービス管理者のYさん。
これを読んでくださっている皆さんの中にも「わかる~!」という方、多いのではないでしょうか。
【利用者を増やす㊙営業術】第12回 稼働率が上がらないのは定員枠やサービス種別が適正ではないからかも Part1
利用者登録数は十分あるのに稼働率だけなかなか上がらない理由

みなさんの事業所の定員数は何名ですか?
その定員数に対して毎日平均して何名のご利用者が計画上通所予定になっていますか?
その中から何名が実際に通所利用して下さっていますか?
重要なのはこの実際部分です。
この実際の数字は「定員」という基準で上限が規定されており
同一時間においてそれを上回る稼働をしてはいけません。
つまり計画段階でそれを上回る稼働が組めないのです。
稼働率が上がらない理由は、管理者の営業努力が不足しているだけではありません。
構造上の問題もかなり大きな要素を占めてきます。
今回は、このジレンマについて
・営業利益
・期待値
という2点で解説をさせて頂きます。
私自身の改善経験も踏まえて話を進めて参りますので、ぜひ参考にして頂き
稼働率を高めていって頂けると嬉しいです。
第197回社会保障審議会介護給付費分科会を傍聴して
月刊デイ編集長:妹尾弘幸の報告
2020年12月18日(金)に「第197回介護給付費分科会」が開催されました。
本年最後の分科会は「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」について、協議されました。
最後の分科会ということもあり、意見は少なかったのですが、やはり最後まで話題となったのは、「ICT、ロボット等の活用による業務革新」「業務の効率化」についてでした。
【利用者を増やす㊙営業術】第11回 既存顧客を攻略しキャンセル率を下げるべし Part.2
Part.1の復習とこの記事で紹介すること

前回Part1で出来高モデルのキャンセル止めについて解説をしました。
出来高モデルの特徴は「来た分だけ売上になる」ということで
・通いたい理由を作る
・通えない理由を無くす
ということについて攻略していく必要がありましたね?
通いたい理由を作るということは
・行っても暇
・やりたいことはさせてもらえない
・やりたくないことばかりさせられる
・やっていることが何のためなのか分からない
・いじめられたり不快な気持ちにさせられる
・自分をわかってもらえない
このような条件を潰していくことが大切で
・ボーっと座っている時間を無くして、活動して頂く
・ご利用者の目標を達成するために必要な訓練・活動を提供する
・一日中「歌」「ぬり絵」「漢字・計算ドリル」「筋トレマシン」はNG
・旅行にいくことが目標なのに、一日中「ぬり絵」をさせられている
・進捗状況が分からない → どこまで良くなったのか知ることができない
・自分のタイミングで介助してもらえない、言っていることが分かってもらえない
このような条件を全てクリアにしていく必要性があるということをお伝えしました。
今回は、包括報酬モデルのキャンセル止めについて解説をしていきますが
出来高モデルとは少し要素が異なるため、今回の記事を活用して対応して頂ければと思います。
第196回社会保障審議会介護給付費分科会を傍聴して
月刊デイ編集長:妹尾弘幸の報告
2020年12月9日(水)に「第196回介護給付費分科会」が開催されました。
今回のテーマは下記について主に話し合われました。
以下の点で方向性が議論されました。
【1】認知症グループホームの夜勤3ユニット2名で可能とする
【2】特養ユニット型の定員を10名から15名に増員する
【3】見守りセンサー等導入による人員基準緩和
→(1) 特養夜勤職員基準…25人以下夜勤1名を30人以下夜勤1名など
→(2)夜勤職員配置加算…100%導入時 夜勤者最低基準に加えユニット型の場合0.6とする(特養、老健)、15%導入を10%導入に緩和0.9人(特養、老健、介護院、グループホーム)
【4】令和3年度介護報酬改定に関する審議報告書案について
前回に引き続きICT活用による人員基準緩和について、賛否が分かれました。
各委員はICTの導入による効率化などには反対はしていませんが、人員基準の緩和については、経営サイドである特養、老健協会は賛成、労組や家族の会、職能団体などは反対という立場をとっており、これについては引き続き議論がされていきます。
また、審議報告書案で、リハビリ、機能訓練については、以下のように書かれています。