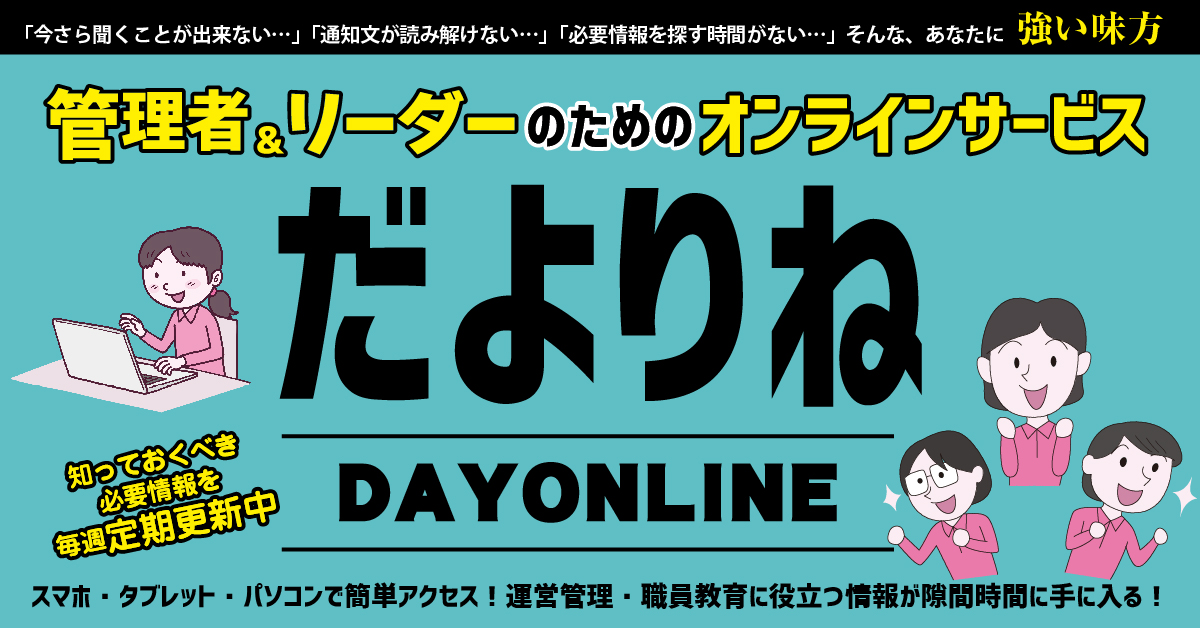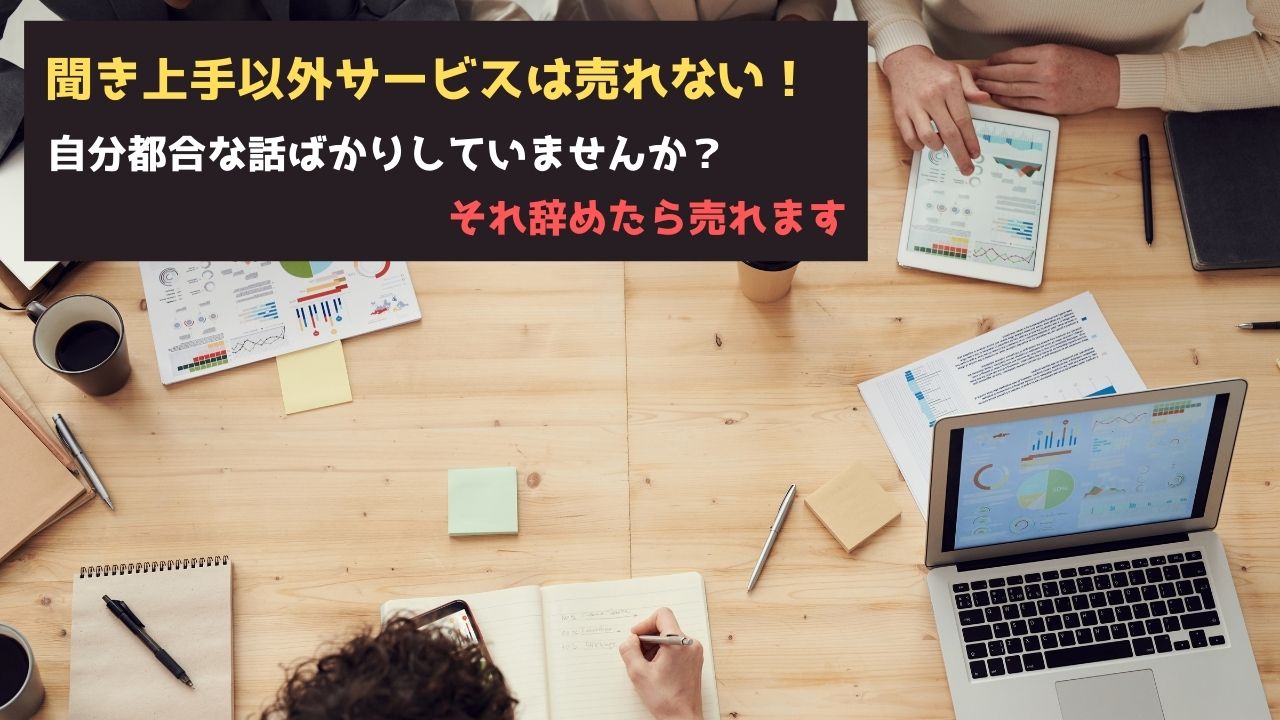【介護保険制度改正・介護報酬改定ミニ講座】見落とすと危ない…共生社会実現に向けた法律改正ついて
令和3年4月より共生社会実現に向けた法律改正が施行されます
共生社会実現に向けた法律が改正され(令和2年6月12日 法律第52号)、令和3年4月1日より施行されます。
今回はこの法律について紹介していきたいと思います。
共生社会実現に向けた法律改正
一億総活躍プラン(平成28年6月2日 閣議決定)の中で、地域共生社会の推進が決定されました。
それを受けて、共生社会実現に向けた法律が令和2年6月12日に改正され、令和3年4月1日より施行されます。
【利用者を増やす㊙営業術】第17回 令和3年度介護報酬改定後にするべき営業について【老健編】
加速する医介連携の中心を目指す

以前から強化に強化を重ねてきた医介連携ですが、実質的な連携が図れていたかと言えば
疑問を感じる結果になっていると思います。
もちろん、地域によっては実質的な連携が出来ている所もあると思いますが、それは制度の整備状況や浸透具合というより
1人ひとりの担当者が持つ能力による所が多く、誰かがリーダーシップを持って動かなければ地域における医介連携は進んでいかない
そう思っています。
・医介連携ってそもそも何?
・どんなメリットがあるの?
・何も考えてなくても勝手に利用者は回ってくるでしょ
こういった"他人事"の方も、もちろんいらっしゃると思いますし、それを悪いことだとは言いません。
ただ、地域の医介連携に向けて一歩前進した法人は、地域で明らかな医介連携の中心になれると思っています。
なぜなら
お互いがお互いのことをあまり理解していないからです
さらに
基本的にみんな他人事だからです
だからこそ、連携メリットをいち早く"提案"し理解して頂くために、"営業"を行う必要があるのです。
では、具体的に
・誰に
・どういった提案をするべきか
・お互いのメリットは何なのか
これらについて詳しく解説を行っていきます。
【実地指導のいろは】実地指導とは
指導とは何か
デイサービスなどの介護保険サービスを運営する上で、実地指導の知識と理解は欠かせません。
特に管理者は、運営に関するすべてにかかわり、管理する役割があるため、実地指導においても中心となって対応する必要があります。
ここでは実地指導の基本的な知識と、実地指導での事業所運営へのリスクについて紹介します。
【利用者増に向けたちょっとした工夫】「また料理がしたい!」の声を実現させる「環境づくり」→「活動」→「参加」へ
どうしたらあの頃のように本人の自信や意欲を取り戻すことができるのか
「仕事だけでなく昔は家でも料理をやっていたけど、出来なくなってしまった。」
現役時代は板前として働いていたA様。
ご家族からは、
「以前は料理を作るのに手伝ってくれていたが、最近は手伝ってくれなくなった。」
との声が聞かれたため、当事業所では「どうしたらあの頃のように本人の自信や意欲を取り戻すことができるのか」と考え関わりはじめました。
情報提供:ありがとうミラクルデイサービス(広島県福山市)
【介護保険制度改正・介護報酬改定ミニ講座】入浴介助加算について
2021年4月より入浴介助加算が(Ⅰ)(Ⅱ)となります
2021年1月18日(月)に社会保障審議会介護給付費分科会(第199回)が開催され、新年度からの報酬単価が発表されました。
今改定は通所系サービスにとって大きな変化となりました。
その中でも入浴介助加算の(Ⅰ)(Ⅱ)が挙げられます。
現行の入浴介助加算は50単位でしたが、新年度からは入浴介助加算ⅠとⅡの2種類が新設されたことにより、自宅での入浴自立等を目指した入浴介助が求められます。
居宅訪問を行い自宅の「浴室環境」「入浴行為の評価」「個別の入浴計画の作成」が算定要件に義務付けられました。
これに伴い入浴介助加算(Ⅰ):40単位(-10単位)、入浴介助加算(Ⅱ):55単位(+5単位)となっています。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」等の令和3年度における取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱い第12報(令和2年6月1日)、第13報(令和2年6月15日)発出の臨時的な取扱いは、2021年3月廃止
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱い第12報(令和2年6月1日)「通所介護費等の請求単位数について」、第13報(令和2年6月15日)「問1-3」で発出されている臨時的な取扱いについては、2021年3月のサービス提供分をもって廃止となります。
【利用者を増やす㊙営業術】第16回 新規利用者を獲得できる担当者はみな聞き上手
一方的にベラベラと話をする担当者は売れない
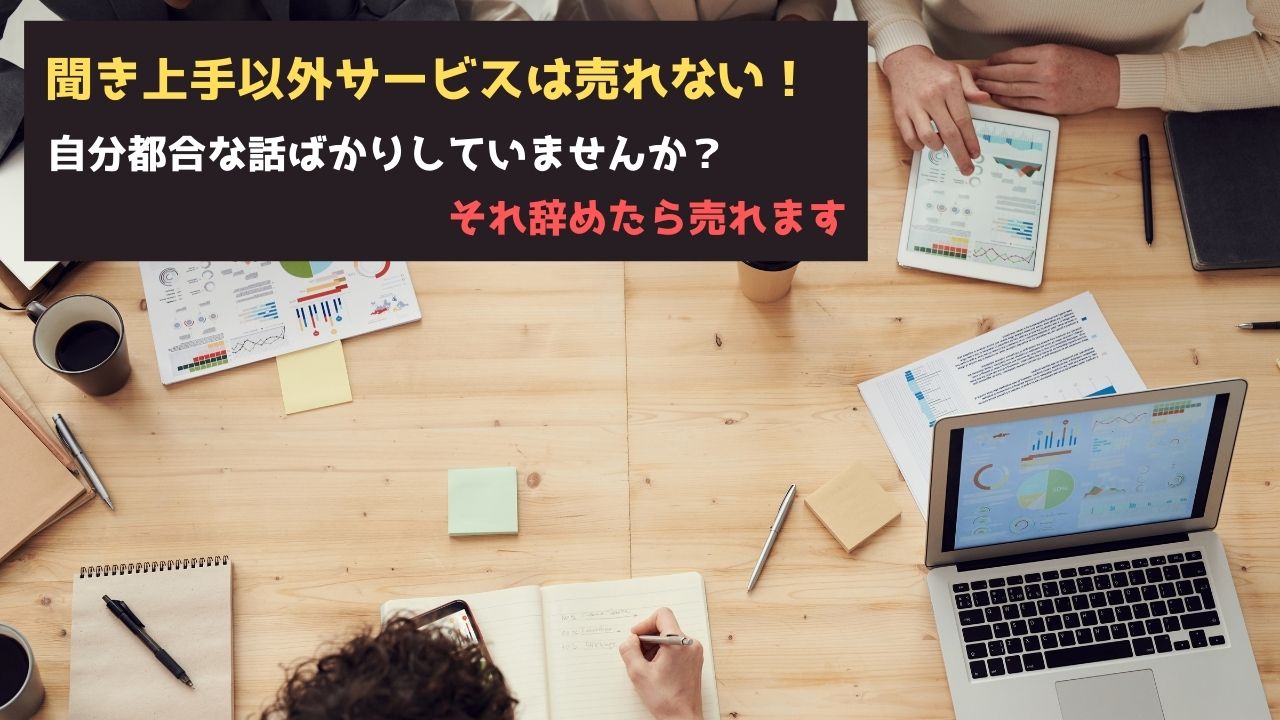
みなさん8対2の法則ってご存知ですか?
ネットで検索すると「パレートの法則」が出ますが、今回お伝えしたいのは優先顧客を導き出す方法論ではありません。
商談が上手くまとまる会話のバランスについて紹介したいと思っています。
みなさん一方的に自分の話ばかりしていませんか?
事前に調査した内容や、勝手な決めつけ、思い込み、統計データ、平均値を振りかざして
◯◯ですよね?だからウチのデイが良いと思うんです!って決めつけていませんか?
これは、×です!
なぜなら、自分と関係性のない他人にいきなり一方的にベラベラと話をされても"つまらない"からです。
商談が上手くいった場合の会話は全て"面白い!"し"相手もニコニコ"しています。
玄関先まで送り届けて手を振って下さることも良くあります。
これ、なぜだか分かりますか?
成果を上げる良い営業担当者ほど、相手との距離感や関係性の深耕度合い(リレーションシップ)をとても気にしているからです。
はい!抽象的ですよね(笑)
今回は、「成果を上げる営業担当者」が意識している会話のバランスや法則、その内容について詳細に説明させて頂きます。
ぜひ、最後までご覧いただき、"今日からの営業活動"に活かして頂きたいと思います。
第199回社会保障審議会介護給付費分科会を傍聴して
月刊デイ編集長:妹尾弘幸の報告
2021年1月18日(月)に「第199回介護給付費分科会」が開催されました。
今回は、新年度からの新しい報酬単価が発表されました。
通常規模型の通所介護では、7-8時間の要介護1で648単位から655単位へと7単位のプラスとなりました。
通常規模型の通所介護の基本報酬プラス分は、3-4、4-5時間で4単位、5-6、6-7時間が6単位、7-8、8-9時間が7単位でした。
大規模型通所介護はそれより1単位低いプラス幅となっています。
第198回社会保障審議会介護給付費分科会を傍聴して
月刊デイ編集長:妹尾弘幸の報告
2021年1月13日(水)に「第198回介護給付費分科会」が開催されました。
今回は、介護給付費分科会の親会議である「社会保障審議会」に提出する諮問書の審議でした。
具体的には、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」についての最終確認です。
すでに今まで議論されたことをまとめた文書について了承を得るための会議なので、異論も出ず了承されました。
その内容は下記の通りです。
(今までの経過と変化はありませんでした)
報酬単価は今月中に発表されると思われます。
【利用者を増やす㊙営業術】第15回 成果を上げたいなら清潔感と目と声を意識して!
成果がでない営業担当者には"ある特徴"がある

営業活動において、絶対にしなければいけないことは何か・・・
これは何度もお伝えしていることですが、"ポジションを保つこと"です。
ようは、相手を不快にしないことが安定した成果を出すために重要な要素となります。
相手が当たり前だと思っていることを当たり前にできているか!
正直もうこれだけです(笑)
ただ、それを理解して
丁寧な対応を心がけ素晴らしい提案ができていたとしても、成果がなかなか出ないこともあります。
なぜでしょうか・・・・
これはあくまで私の主観となりますが、「清潔感」と「熱量」が不足している場合は、成果が安定しない
と思っています。
特に女性の方は"清潔感アンテナをバシバシ発信している"ので、あらゆるところをチェックされてい
ると思った方が良いですし、目や声質は情報や提案者の信頼性を高めるために非常に重要な要素となるた
め、とある意識をする必要があります。
今回の記事では
・清潔感チェックをクリアするための具体的な対策について(どこを見られているかも合わせて)
・目はどこに向けて、声質はどのように変化させることがベストであるか
これらについて分かりやすく紹介させて頂きます!
ぜひ、活用してアウトプットして頂ければ幸いです。