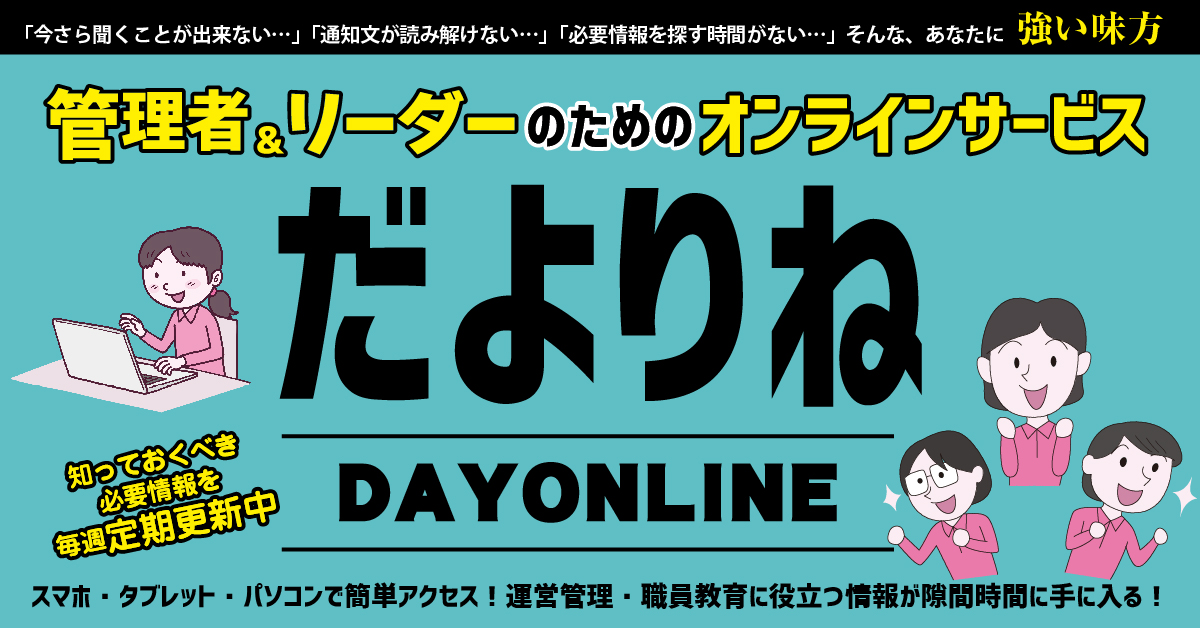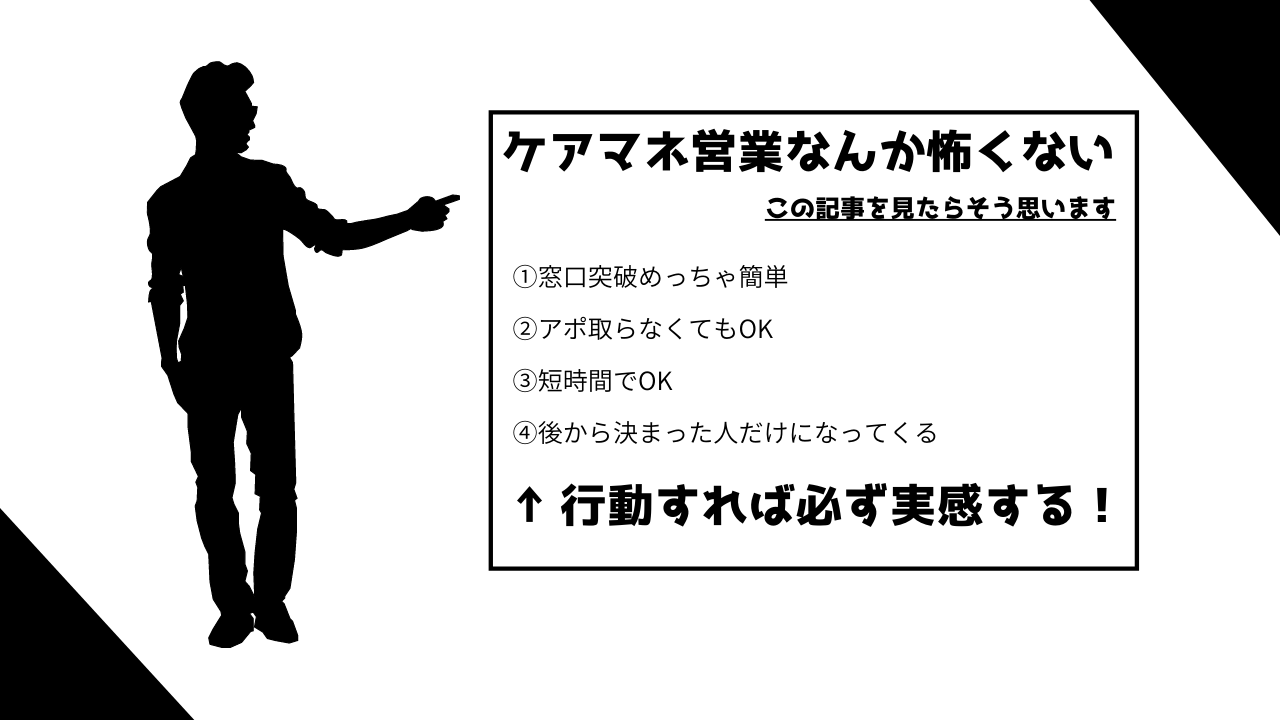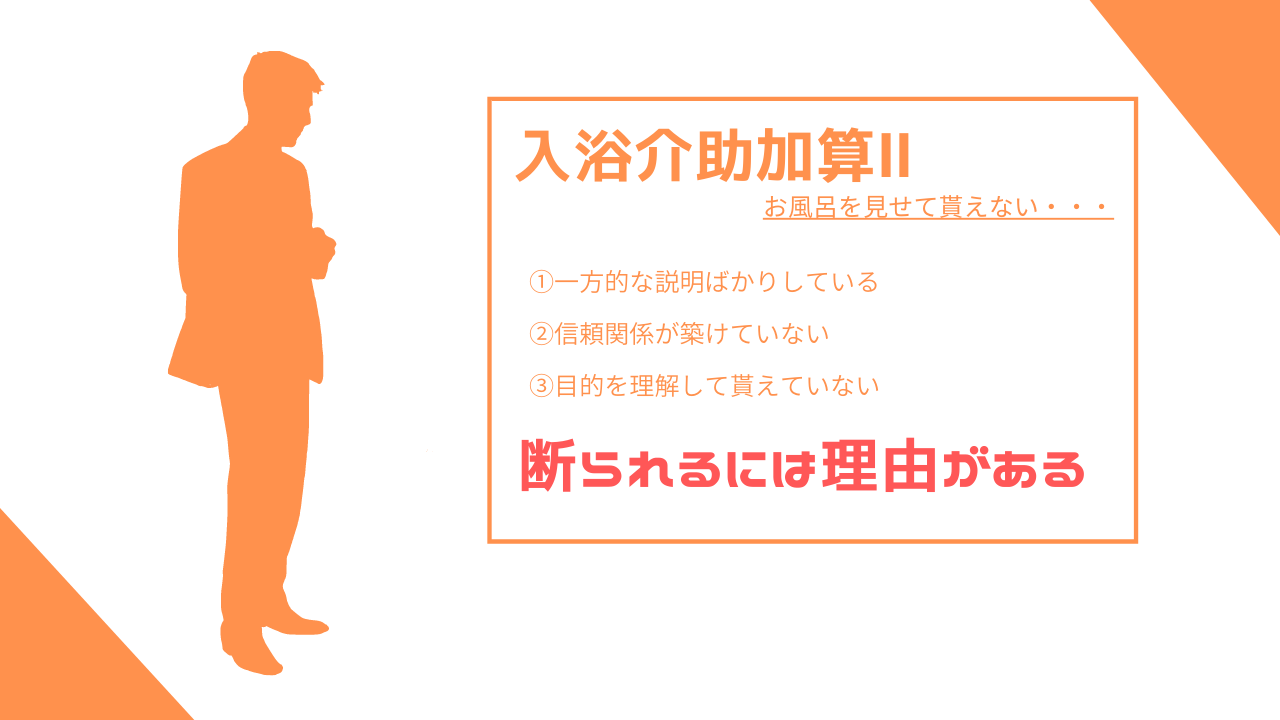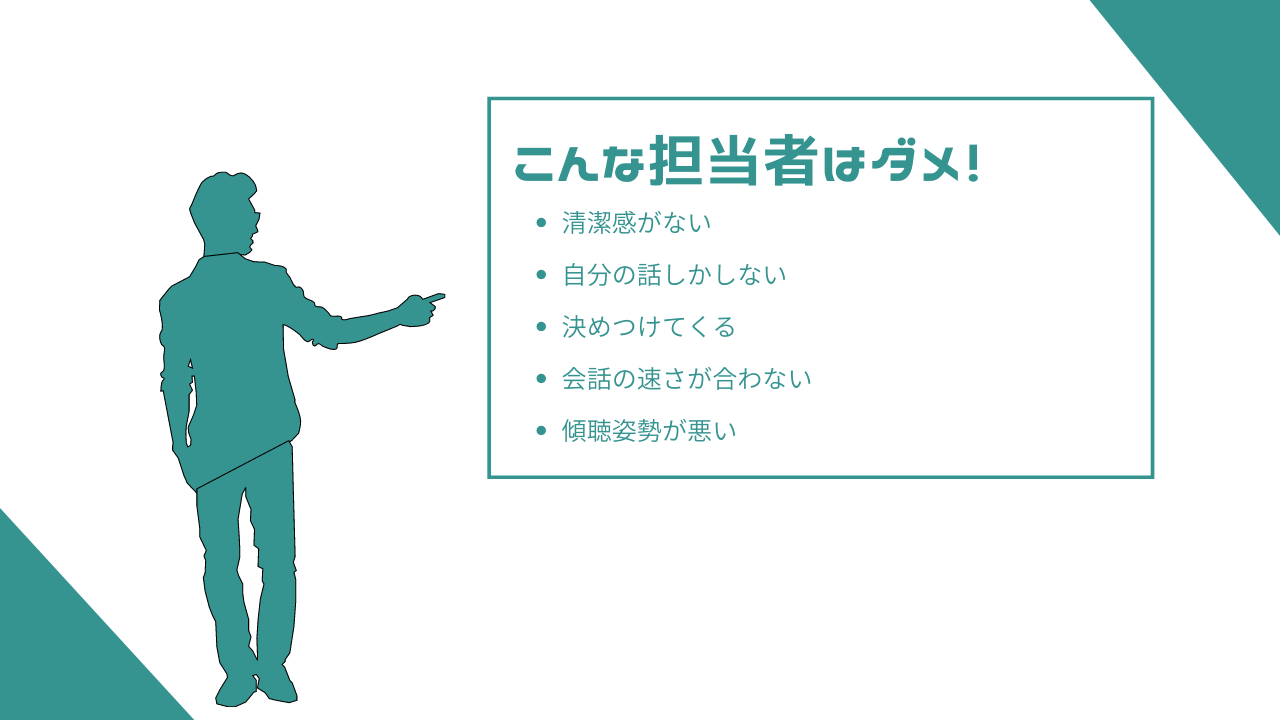【労務管理の落し穴】足を滑らせてけがをした場合、休業中の賃金はどう計算するの?
【事例】
Yデイサービスセンターでパートタイマーとして勤務しているNさん(勤続年数8年)が、ご利用者を介助中、濡れた床で足を滑らせて転倒し、左腕を骨折するけがを負ってしまいました。
2ヶ月間休業となり、休業補償給付の手続きを行っています。
月給制の場合の平均賃金の計算は簡単なのですが、Nさんは時間給制(1時間900円)で週1回勤務、1日の勤務時間は8時間です。
こういった短時間勤務の方の平均賃金はどのように計算すれば良いのでしょうか?
入浴介助加算のQ&Aは今週末から来週に発出予定
入浴介助加算(Ⅱ)の算定を取りやすく
2021年4月7日(水)に横浜で行われた日本在宅介護協会主催の報酬改定セミナーで、講師の厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課の平井氏は「入浴介助加算(Ⅱ)は、自立支援の入浴介助の視点を広めるため、算定しやすくなるようにQ&Aが発出される見込み」「発出は今週末から来週になる予定」と発言しました。
【利用者を増やす㊙営業術】第24回 この記事を見たらケアマネ営業が怖くなくなります
今回の記事の目的
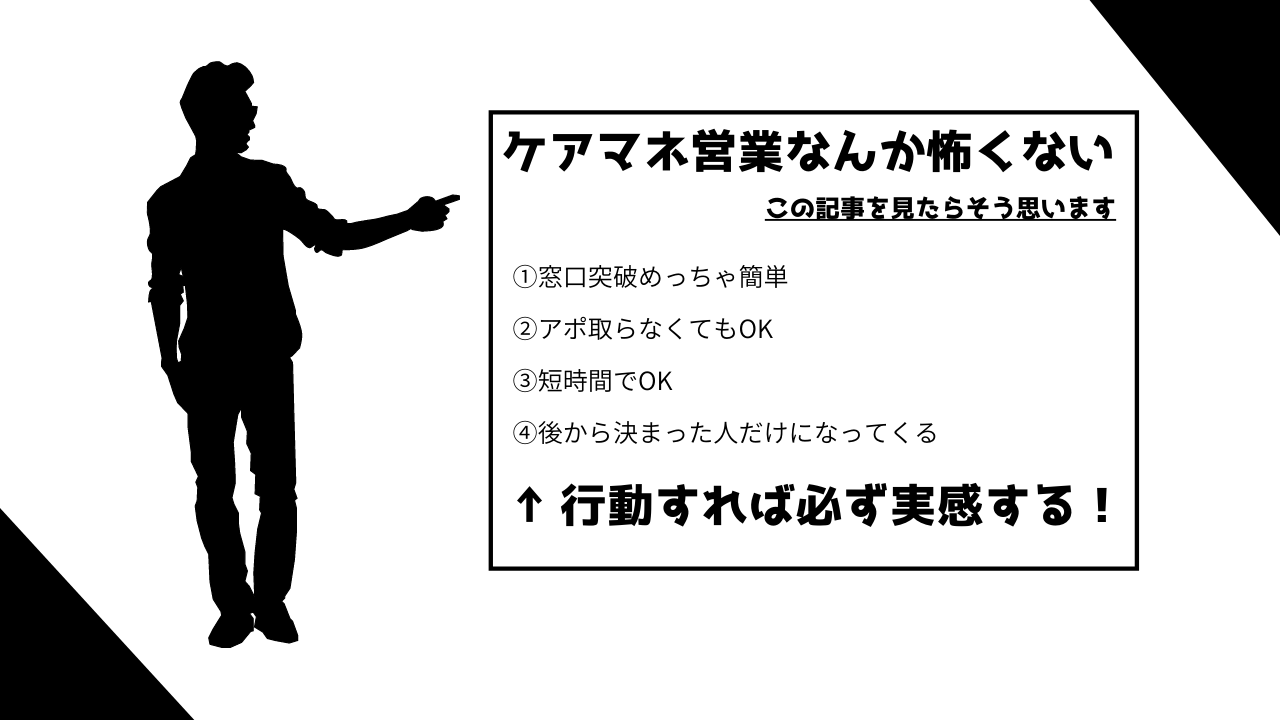
営業職として仕事をしている訳ではないけれど、ご利用者を獲得していくためには必要不可欠なのが営業。
日々、ご利用者に良いケアを提供したいだけなのに、営業なんてなんでしなければいけないのか・・・
と、憂鬱な気持ちになる方もいる事でしょう。
ケアマネさんの所に行って何て話をすればいいのか・・・
どんな提案をすればいいのか・・・
何もかもが分からないことで、憂鬱な気持ちになっているのかもしれません。
今回の記事では、読んでくださった皆さんが「ケアマネ営業が憂鬱じゃなくなる」を目標に、以下のことについて解説をしていきます。
・ケアマネ営業は窓口突破がめちゃくちゃ簡単で怖くない
・基本的にローラー営業で良いので手間がかからない
・短時間でいかに印象を残せるかが重要であり、営業マンっぽいトークスキルは必要ない
・ルート営業に切り替えてからが勝負なので、そこまでは種まき感覚で良い
【再確認】個別機能訓練加算と入浴介助加算について
新しい報酬体系でス新年度がスタートしました。
算定要件などの間違いによる誤請求・返還などがありますので、再度確認しておきましょう。
入浴介助加算のポイント(Q&Aは2021年4月4日(日)時点で出ていません)
【1】(Ⅱ)はa)自宅アセスメント、b)個別計画書作成、c)個浴などでの入浴介助を評価するもの
【2】介助には観察も含まれる[(Ⅱ)は(Ⅰ)を準用するため]
【3】居宅において自身・家族またはヘルパー等の介助で入浴できるようになることが目的
個別機能訓練加算のポイント
【1】人員基準・・・管理者が個別機能訓練加算の職員を兼務することはできない。
【2】訓練指導員が1名の時間帯は、加算Ⅰ(ロ)85単位が請求できない。
【3】4月から加算をとるためには計画書を作り直さなければいけない。
【労務管理の落し穴】ご利用者宅で飼い犬にかまれた場合、どんな届けが必要なの?
【事例】
Yデイサービスセンターに勤務する介護スタッフFさんがご利用者を自宅までお送りしていたところ、玄関にいた飼い犬に左足をかまれてけがをしたため、病院に行きました。
仕事中の災害ということで労災の申請をしましたが、後日、労働基準監督署から今回の労災申請は第三者行為災害になるため、「第三者行為災害届」と「念書(兼同意書)」の届出をするようにとの文書が来ました。第三者行為災害というものを初めて聞いたのですが、いったいどういうことなのでしょうか?
管理者と加算指導員の兼務不可!!個別(Ⅰ)イ・ロ算定は計画書見直し必要「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(機能訓練に関係すること)」
2021年3月26日に報酬改定Q&A Vol.3が発出されました。
その中で機能訓練関係のQ&Aは20問と最多の分野となっていました。
以下、ポイントを列挙します。
【利用者を増やす㊙営業術】第23回 【報酬改定対応】お風呂を見せてくれない!それちゃんと説明できていますか?
一方的な話になっていませんか?
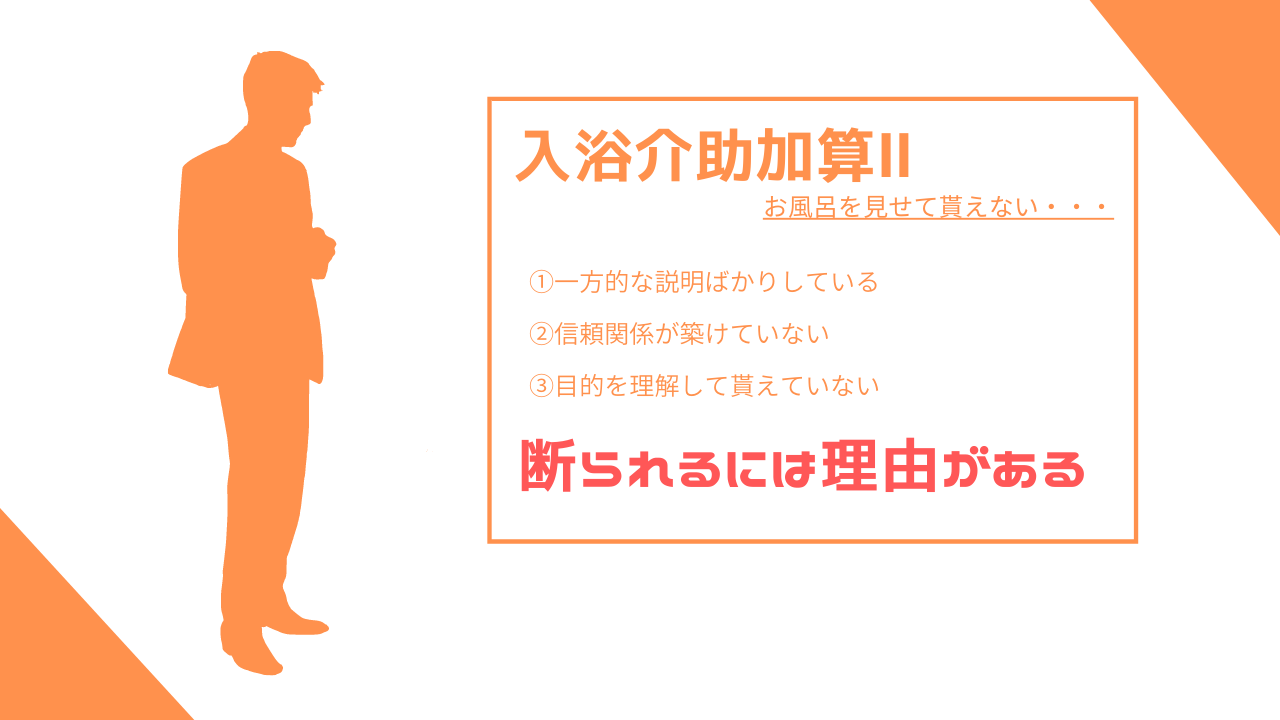
2021年度の介護報酬・制度改定で入浴介助加算に区分が設けられました。
入浴介助加算Ⅰ(40単位)・・・入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有して入浴介助を行う
入浴介助加算Ⅱ(55単位)・・・入浴計画に基づき居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと
上記の入浴介助加算Ⅱを算定するために、ご利用者の浴室を見せて頂くためのお願いをして、断られている方はいらっしゃいませんか?
それには明確な理由があると思います。
結論、断られる理由は以下の3点になると思います。
①一方的な説明ばかりしている
②信頼関係が築けていない
③目的を理解して貰えていない
①一方的な説明ばかりしている
皆さんも、自分に必要性があるかないか分からないものを押し売りされたら買いませんよね?
家に外壁塗装の訪問営業が来て、「◯◯さんのお家を見る限り、そろそろ塗り替え時なので、塗り替えても良いですか?」
って言われたら、不快に感じるはずです。
なぜ、あなたに塗り替え時を決められないといけないの?
金額も色も塗料も工期も、必要な相談事が何もないのに、なんで今すぐ答えを出さないといけないの?
このような疑問が浮かび上がり、それは憤りとなって目の前の営業担当者を叱る方もいらっしゃるでしょう。
営業担当者は「プロ」なので、塗り替えの必要性を理解していますが、目の前の顧客は「素人」なので「感性的に解釈」するしかない訳です。
なので、「◯◯さん、4月から入浴をして頂くのに必要なので、ご自宅のお風呂を見せて頂いても良いですか?」という一方的な
内容をご利用者に伝えることは避けた方が良いと思います!
重要なのは「会話の中で相手に決めて貰うこと」です!
そもそも、目の前のご利用者は「自分1人で自宅のお風呂に入りたいと思っているのか」というニーズを引き出さなければいけません。
そして、仮に「入りたくない!」と言われたとしても、それが本心なのか、何かを気にして心に蓋をしてしまっているのかを見極めて適切な方向に導いてあげることをしなければいけません。
その努力を怠って、一方的に加算を算定しようとすることは「押し売り」と一緒なのです。
必ず、会話の中でご利用者に答えを出して頂く努力をするようにしましょう!
科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方と事務処理手順
科学的介護情報システムに関連する各加算の算定については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12 年3月1日老企第36 号。以下「訪問通所サービス通知」という。)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12 年3月8日老企第40 号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18 年3月17 日老計発第0317001 号、老振発第0317001 号、老老発第0317001 号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18 年3月31日老計発第0331005 号、老振発第0331005 号、老老発第0331018 号)及び「特別診療費の算定に関する留意事項について」(平成30 年4月25 日老老発0425 第2号)示されており、基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例が公表されましたので、各データ提出関連加算の漏れがないよう留意してください。
通所系サービス関連のデータ提出加算の「提出情報」「提出頻度」などを抜粋し、ご紹介いたします。
【1】科学的介護推進体制加算
【2】個別機能訓練加算(Ⅱ)
【3】ADL維持等加算
【4】栄養アセスメント加算
【5】口腔機能向上加算(Ⅱ)
【利用者を増やす㊙営業術】第22回 全く話にならない営業担当者5選!
全く話にならない営業担当者は何がダメなのか?
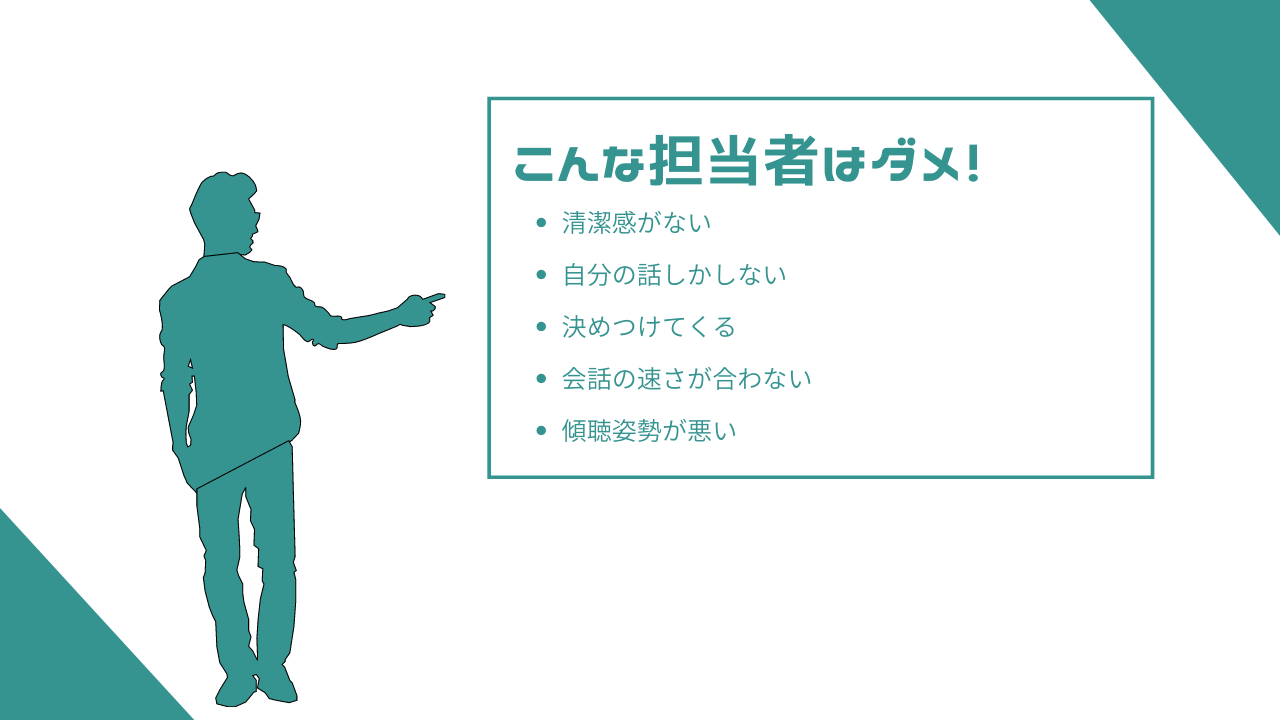
みなさんも、介護業界に限らず、様々な営業担当者と接点を持ってこられたと思いますが、
この営業担当者キツイなーと感じたことありませんか?
結論、以下の5つの特徴に当てはまる営業をしている人は・・・正直キツイと思われているはずです!
① 清潔感が無い
② 自分の話しかしない(質問してこない)
③ 決めつけてくる
④ 会話の速さが合わない(被せてくる、遅すぎる)
⑤ 傾聴姿勢が悪い
今回の記事は、自分の営業や他者との関わり方が
・ダメなのか
・良いのか
という単純なフィルター作業だけでなく、それを改善し
スーパー営業担当者になれるような前向きな記事にしていきたいと考えています!
↓ それぞれのダメポイントの理由
↓ 相手への捉えられ方
↓ 具体的な改善方法
このような順番で分かりやすく解説をしていきますので、ぜひ最後まで読んで頂き
研修等で活用頂ければ嬉しいです。
【実地指導のいろは】日ごろから記録を大切にする
記録はサービス提供を証明する重要なもの
デイサービスをはじめ、介護サービスは日ごろの業務の中でたくさんの記録を行っています。
実地指導では、記録でサービス提供状況などを確認するため、市役所などから来た担当者は時間をかけてこの記録を確認します。
いくら現場でよいサービスを提供していたとしても、記録がない、不備があるなどの場合は指導を受けることになります。
サービス提供の記録や通所介護計画など、記載しなければならない事項が次のように基準に定められていることもあります。
また、条例や通知などで記録するように求められている事項もあるため、よく確認して記録を整備しましょう。