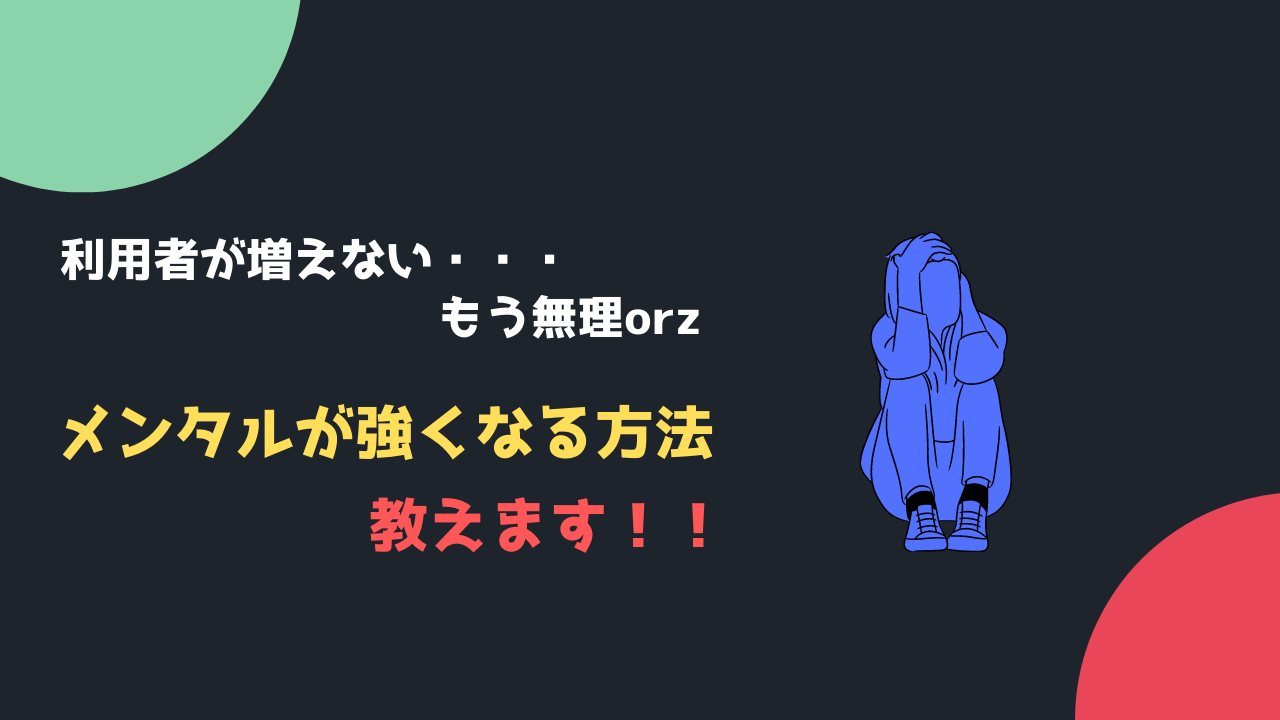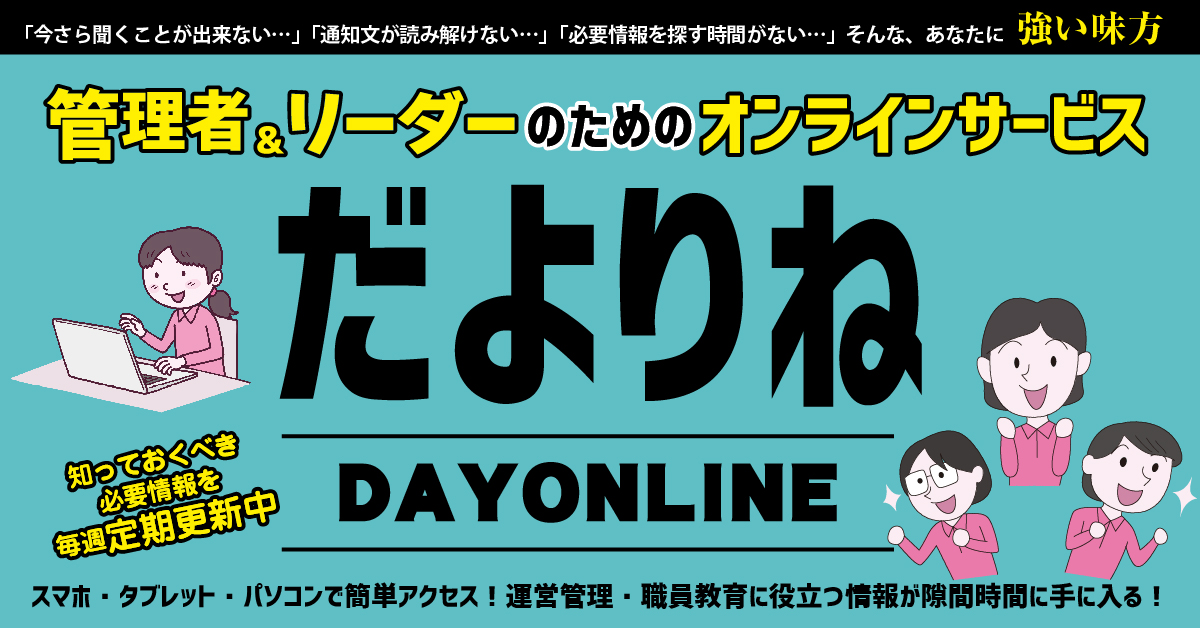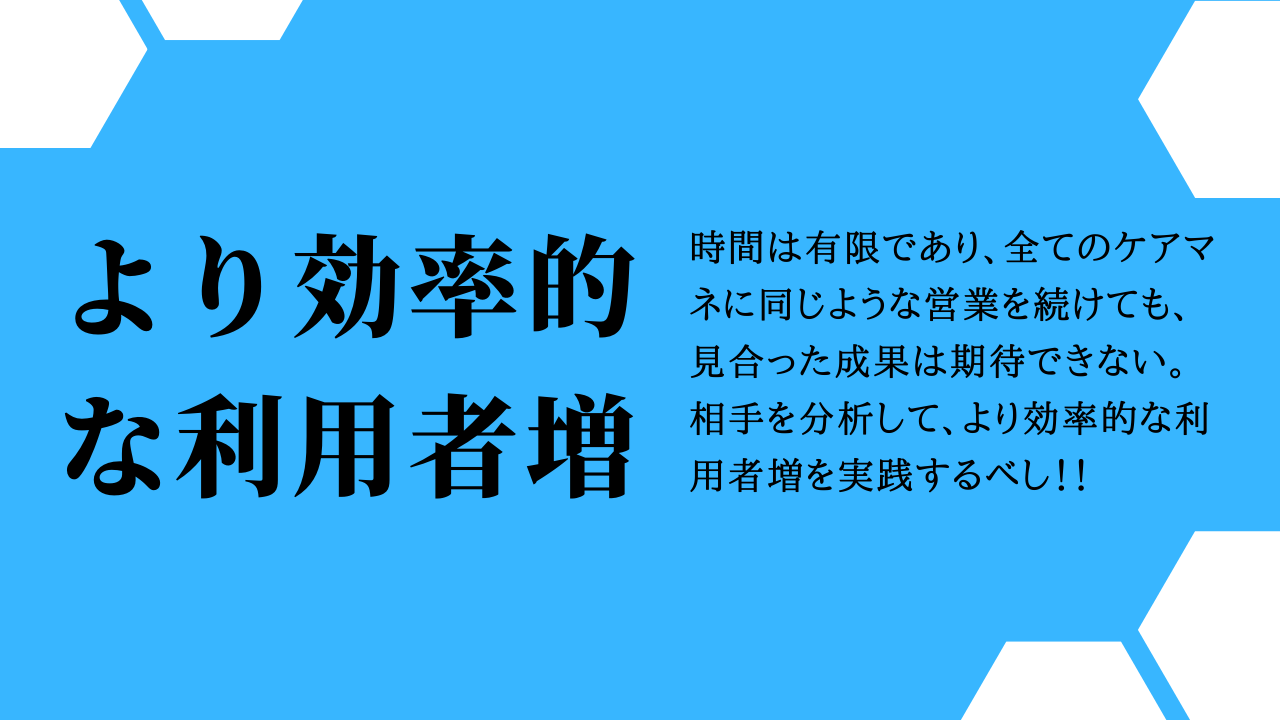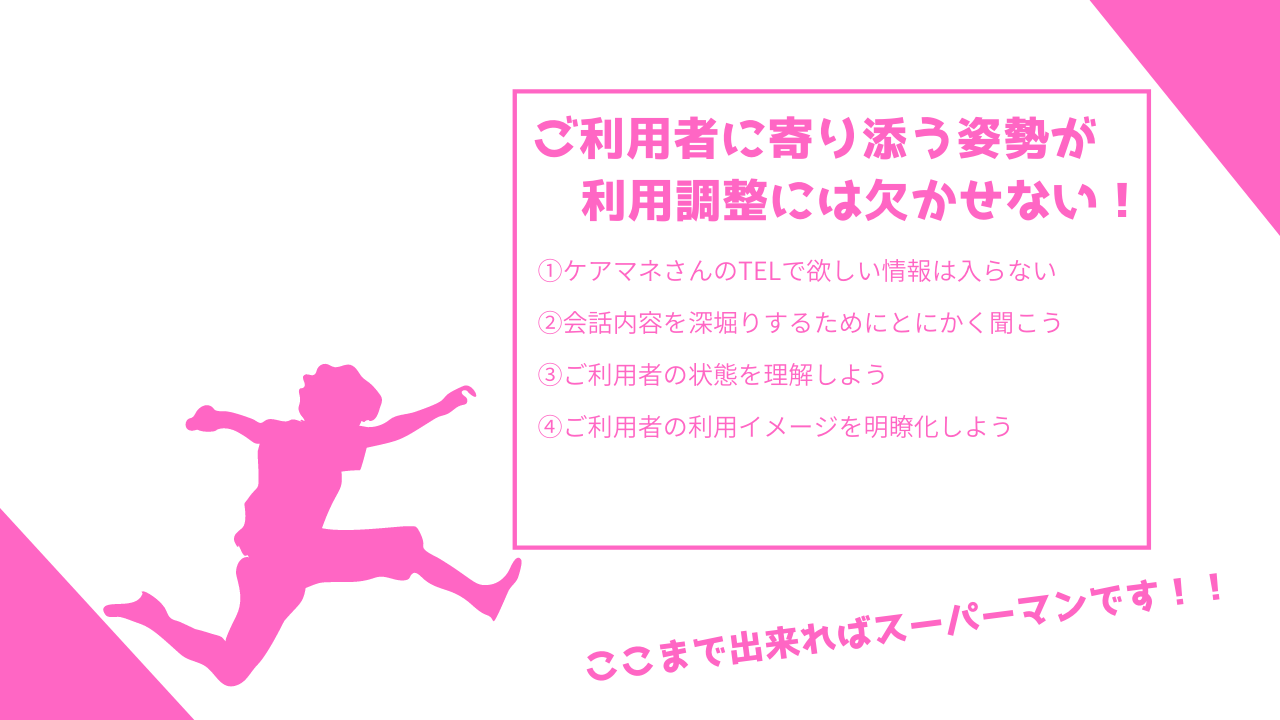【利用者を増やす㊙営業術】第27回 利用者が増えない・・・メンタルが落ち込んだ時の切り替え方について
営業で最も重要なのはメンタル
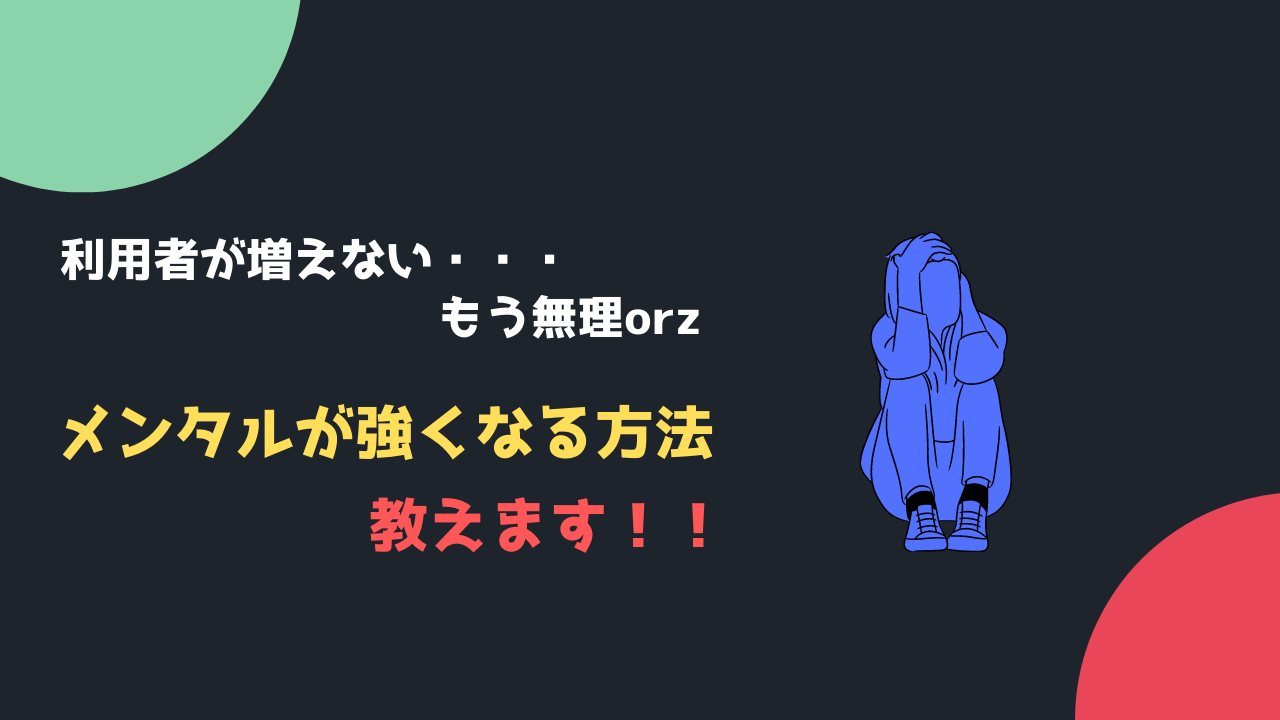
開口一番に精神論ですみません(笑)
ただ、これは紛れもない事実で、営業活動を行う上で最も重要となって来る要素は
メンタルの強さです!
正確には、「メンタルが強い」なんて人いないと思います。
みんな、強い口調で否定されたり、一方的に言われたり、利用調整が上手くいかなかったり、成果が出なかったりすると
100%気持ちが沈みます。
これは、継続的に成果を出し続けている営業担当者や管理者さんも同じです。
ただ、2点を除いては・・・
結論から言うと、「メンタル強いよな―あの人」と思われている敏腕営業担当者や管理者は
・気持ちが落ちないような環境下で結果を追っている
・気持ちを切り替えるルーティンを持っている
この2点がしっかりできている人が多いです。
というよりは、この2点がしっかりできていれば「メンタル」相当強くなります!(笑)
今回の記事では、メンタルが落ち込んだ時の切り替え方について上記2点を重点的に解説していきます。
活用して頂くことで、必ず昨日より強い自分に出会えると思いますので、最後まで読んでみてください!
ご利用者に「活動と参加」に関心を向けてもらうための工夫と対応
通所リハビリテーションや通所介護に通う利用者の中には、身体機能の改善や訓練すること自体が目的になっている方がおられます。
体を鍛えることは悪いことではありませんが、せっかく行っているその訓練が実生活には反映されないこともよくあります。
そのような場合、利用者のご家族から「主人は施設では頑張っているようですが、自宅では何もせずに寝てばかりいるんですよ」など、訓練の実施状況と自宅での生活の実態に相違があることもよく聞きます。
その背景には自宅での役割消失と、それに伴う意欲の低下、やりたいことの不明確さや諦めがあります。
さらに、セラピストのニーズ聴取不足による曖昧な目標設定や訓練の実施等があります。
このような状況の分析・解決ができていないと、「活動と参加」をいくら促しても実施することは困難です。
施設での訓練が本人の生活にとって意味があり、楽しみのある活動と結びつき、「活動と参加」の向上が見られるような対応・方法について紹介します。
【労務管理の落し穴】職員に所持品検査を強制することは可能なの?
【事例】
デイサービス事業所Yのご利用者(Sさん)の家族から、以下の連絡がありました。
「デイサービス利用時に、母(Sさん)に1,000円札2枚が入った財布を持たせていたが、帰宅したときには財布を持っていなかった。本人に聞いても認知症があるためよく分からない。デイサービスに忘れている可能性があるため、調べてほしい」
そこで、職員全員で事業所内、送迎車両内を探しましたが見つかりませんでした。
その旨をご利用者の家族に連絡したところ、「職員が盗んだ可能性があるので、職員個々人を調査しろ」と強い口調で言われました。
当事業所の就業規則には職員に対する所持品検査に関する事項は規定されていませんが、今回は職員全員、拒否することなく検査を受けてくれました。
こういった場合、事業所として職員に対し、所持品検査を求めることは可能だったのでしょうか?
また、それを拒む職員に対し、強制することはできたのでしょうか?
財政制度等審議会財政制度分科会(2021年4月15日)
2021年4月15日(木)に財務省「財政等審議会財政制度分科会」において社会保障についての会議が行われました。
資料では、以下の事項が提案されました。
【提案事項】
(1)要介護1.2の訪問介護、通所介護について地域支援事業への移行を検討すべき
(2)利用者負担を原則2割とすること、2割負担の対象範囲の拡大
(3)ケアマネジメントの利用者負担導入、福祉用具貸与のみのプランは報酬引き下げ
(4)老健、介護医療院、療養病床の室料負担
(5)区分支給限度額対象外となっている加算の見直し
(6)居宅サービスの事前協議制度、指定拒否制度の導入
(7)要支援1~要介護2の居宅療養管理指導サービスの適正化(独歩で通院できない者に限定)
(8)介護サービスの財務諸表等の報告・公表の義務化
(9)地域支援事業の事業費上限超過を厳しく制限すべき
保険外サービスについて
近年、介護保険外サービスへの参入が増加しています。
平成30年9月28日に厚生労働省各課から保険外サービスについての取り扱いについての通知が出されています。【老推発0928第1号 他】
通所介護での保険外サービスについて以下の通り分類し、通知しています。
【1】通所介護サービスを提供中の利用者に保険外サービスを行う場合
【2】通所介護サービスを提供していない時間帯に保険外サービスを行う場合
【3】通所介護利用者と保険外利用者の両者にサービスを提供する場合
【利用者を増やす㊙営業術】第26回 パレートの法則を活用して主要営業先を限定しましょう!
全部に同じ労力をかけるのは非効率
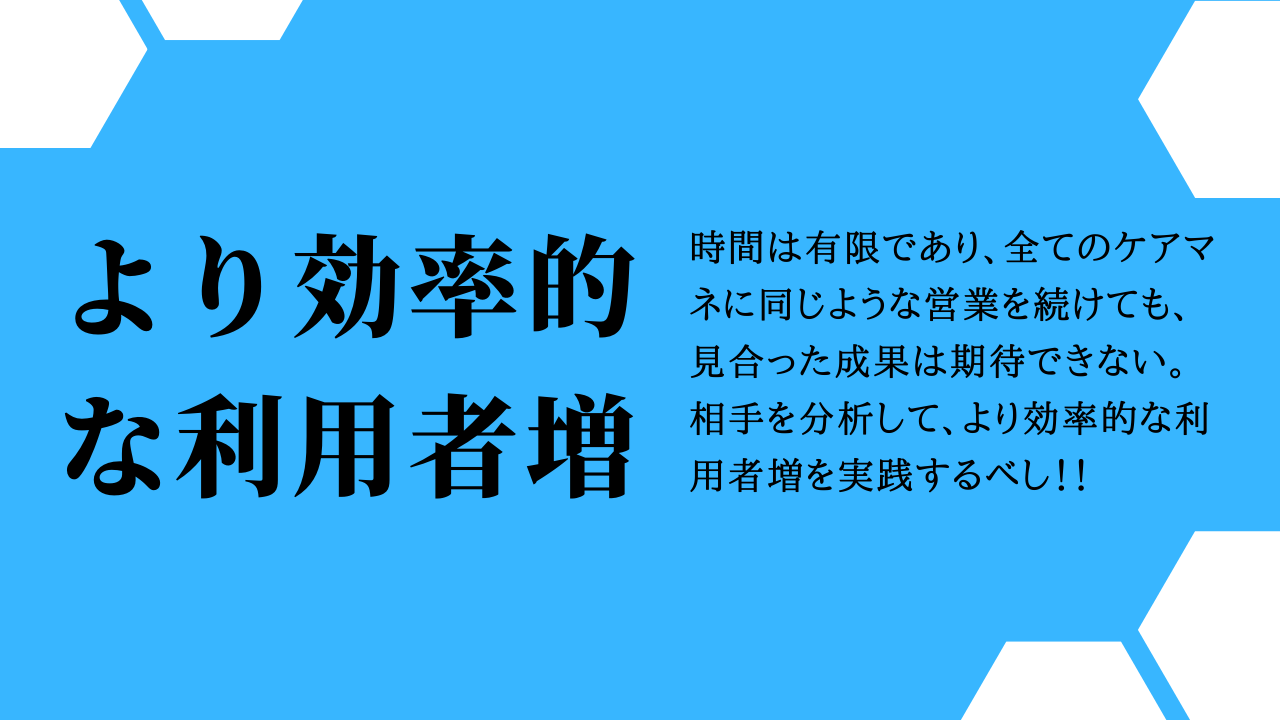
第24回の記事でも掲載しましたが、基本的にケアマネ営業はローラー営業で対応して大丈夫です。
しかしながら、地域にある全ての居宅を訪問していては時間が掛かり過ぎますし、生産性が高くなりません。
新規の営業であれば、時間を取って全ての居宅に訪問していくのも手ですが、2回目以降の営業では力の掛け方を分散
する方が効率的な利用者増が実現できると考えます。
では、どのようにして営業先を優先順位分けしていくかですが
今回は以下の内容について詳しく解説をしていきます。
・勤務しているケアマネの数
・特定事業所加算の算定状況
・実紹介数や相談数、レスポンスの速さや、担当者の能力
今回紹介する内容も利用者増を達成するための営業活動に必ず役立つ情報となっていますので
ぜひ、最後まで読んで頂ければ幸いです。
【その他のおすすめ記事】
・目的を持った営業ができていますか?(特別に営業手法も公開します)
・相手を不快にさせない営業手法を教えます
・店舗ビジネスはPULL営業に上手く動員するべし
この他にも、計22回分のノウハウが会員様限定で公開されておりますので、参考にして頂ければ幸いです。
社内研修やセミナーで活用して頂いてもOKです👍
LIFEへのデータ提出系加算での猶予期間の設定が「されている加算」と「されていない加算」
LIFEへのデータ提出系加算での猶予期間の設定が「されている加算」と「されていない加算」について分けてみました。
全ての加算に猶予期間が設定されているわけではないのでご注意ください
【利用者を増やす㊙営業術】第25回 ケアマネ営業のコツ!「どれだけ利用者に寄り添うことができるか」が鍵!
相手から必要な情報は得られないので積極的に聞き出すことが大切
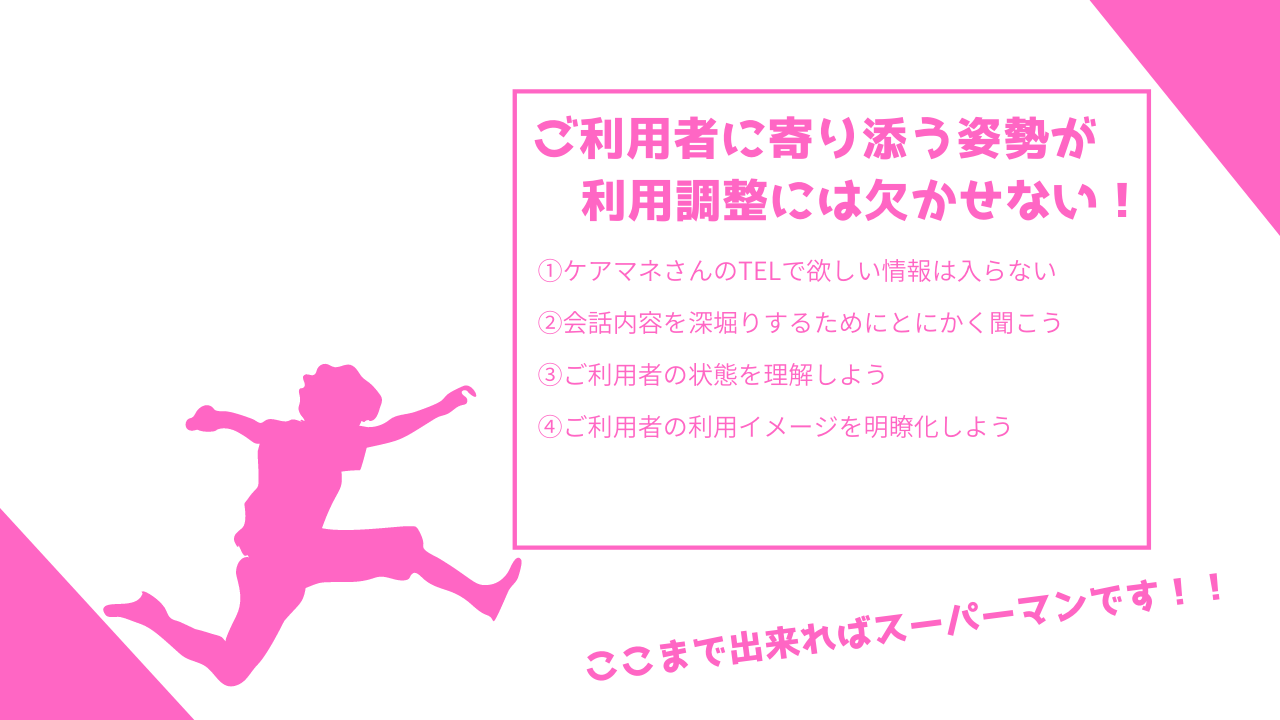
昨日、私の携帯に利用調整の連絡が掛かってきました。
詳しくは個人情報なのでお話できないので、仮設定をして、できるだけ具体的に調整の様子をお伝えできればと思います。
ケアマネ事業所のAさんから以下のような連絡が来ました(笑い話や世間話は省いてお伝えします)。
「相談したい利用者さんがいるんですけど、食事を1ヶ月くらいあまり取られていなくて、筋力も体力も意欲も低下してるんです~
それで、お風呂とかも自分で入られてんなくて、夫婦2人暮らしなんですけどね?それで、奥さん結構シャキッとされている方で、
奥さんが◯◯しなさい!っていうと、もの凄く苛立たれるんです。ただ、私がデイに行ってみよう?っていうと、そうじゃなーって
返してくれるんですよね。」
ここで間が開きました(笑)
さて、利用調整を日々されている皆さんなら、どのように対応しますか?
この記事では、私がこの会話導入からどのように展開をしていったか、何を意識して話をしているかについて解説をしていきます。
みなさんが利用調整を受ける際の参考になると思いますので、最後まで読んで頂ければ嬉しいです。
人員のチェック【職員の配置状況に関する記録】
職員の配置状況については、各記録に差異がないかなど一日ごとに細かくチェックされます。
適正な人員配置の根拠となる人員基準や常勤・非常勤、専従・兼務などの考え方、常勤換算などの計算方法などを理解し、実地指導担当者からの質問に答えられるようにしておくことも重要です。
職員の配置状況は以下の記録で確認されます。
【労務管理の落し穴】中小企業も令和3年度から対象「同一労働同一賃金」
同一労働同一賃金について
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」で、非正規雇用者と正社員での不合理な待遇の差を禁止されることとなりました。
これが、いわゆる同一労働同一賃金です。
中小企業は2021年4月1日より対象となります。
法律改定の主なポイントは以下の通りです。