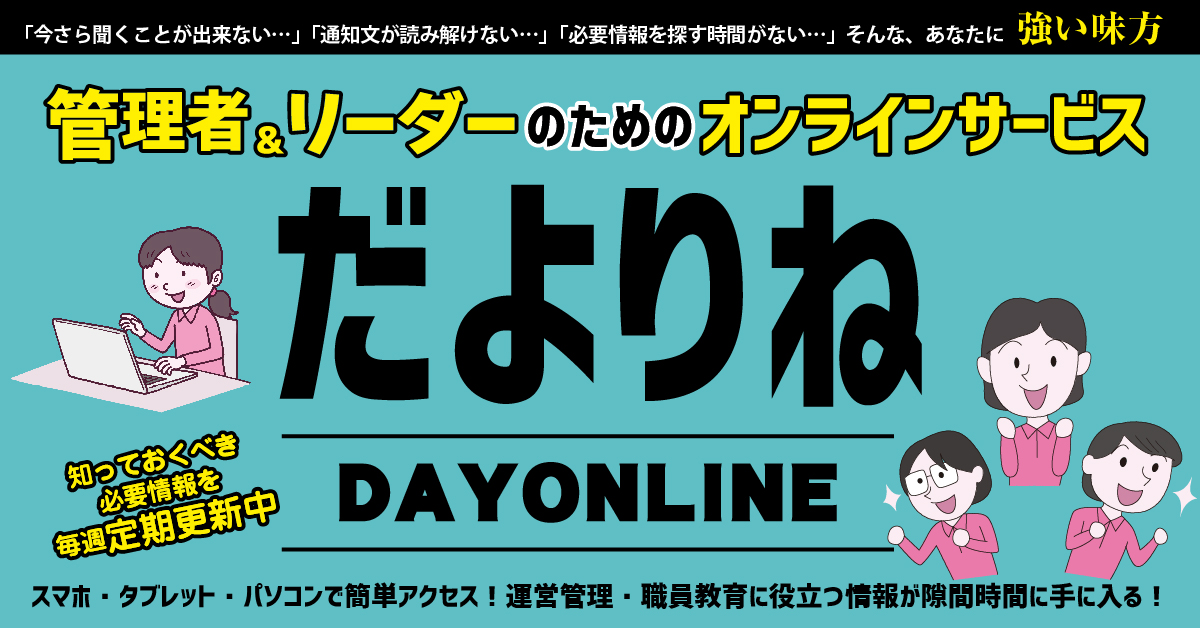【サービスの質向上】アセスメントについて
アセスメントとは、聞き取りや各種評価・測定などによる情報収集をし、各評価やそれぞれの関係について把握、分析し、本人の全体像、本人のニーズを把握することです。
聞き取り・情報収集
本人・家族の希望(ウォンツ)は、重要な情報なので、必ず聞き取り調査します。
本人・家族の希望を聞くことで、本人や家族が、症状、障害、現在の生活をどのようにとらえているか、何を大切にしているか、将来の生活をどう考えているのかなどを推測することも可能です。
細かい言い回しが、心理状態を示していることも多いので、情報はできるだけ本人・家族の言葉そのままの表現で記録してください。
【例】
息子のAさんから「転倒すると入院とか面倒なので、歩く訓練はしないでください」と言われた。
→心理状態として本人の生活改善にはあまり関心がない?
→本人の機能改善よりも入院の費用が気になる?
などが読み取れる
【サービスの質向上】ケアの流れを再確認してますか?
介護では、利用者に関するさまざまな情報を収集し、本人に必要な課題を把握する「アセスメント」を行います。
そして、そのアセスメントを基に、目標と目標を達成するために実施することなどを記載したケアプランを作成し、そのケアプランに沿ってケアを提供していきます。
実施中に、ケアの方向性や内容などについて定期的に監視(モニタリング)し、一定の期間を経た後、再度利用者の状態について評価し、変化や効果を判定します。
ここではこのケアの流れを「アセスメント(A)」「ケアプラン(P)」「実行・モニタリング(D)」「再評価(C)」のAPDCサイクルと定義し、介護現場ではこの流れを繰り返していきます。
【サービスの質向上】モチベーションアップ
ケア場面では、下記の理由などから、本人の意欲を高めることが大切です。
【1】リハビリやケアの効果を高める
(1)実施頻度、継続率、訓練の充実度などが高まる
(2)上記の結果、「目標達成率」が高まる
【2】本人にとってプラスの時間が増える
【3】他者への良好な影響
【4】その他
【サービスの質向上】生活を3つに分類して考える意味
生活を支援するのが介護の役割です。
生活は、さまざまな行為・活動からなります。
私たちは生活の中のどの行為・活動の支援に注力したらよいのでしょうか。
とを求めています。
「生活」の分類
一般的に生活は、「基礎生活」「社会生活」「自由生活」の3つに分類できます。
基礎生活
基礎生活とは、トイレに行く、お風呂に入る、食事をする、寝るなど、いわゆるADLなどの時間です。
社会生活
社会生活とは、働く、学校に行くなどの時間です。 ここでは義務的要素の強い仕事・学業を意味しています。
したがって、趣味の講座に参加する、知的好奇心を満たすために退職後に再び大学に通うなどは自由生活に含みます。
自由生活
自由生活とは、友だちとおしゃべりをする、趣味活動をする、おいしいものを食べに行く、好きなボランティア活動をするなどの時間です。
【サービスの質向上】自立支援で目指すもの
介護保険法では、【有する能力に応じた「自立した日常生活」】ができるよう支援することを求めています。
「有する能力に応じた」とは
本当にその人の能力を引き出しているか?環境の工夫でできることは増える!重度の方にも多くの能力がある!
介護サービスの利用者は、ほぼすべてのことが自分自身でできる方から食事や排せつなど多くのことに介助が必要な方などがいます。
つまり、人によって有する能力はさまざまです。
「有する能力に応じた自立した生活を営むことができるような支援」とは、たとえADLが全介助で寝たきりに近い方でも、その中で自立した日常生活を営めるように支援するということです。
また、本人ができることは環境によっても変わります。
私たちが環境を工夫することで本人ができることも増えます。
【サービスの質向上】忘れてませんか…介護の基本
自立支援の介護とは、「本人がその能力に応じて、自分自身で「豊かな生活・充実した人生を実現すること」を支援する介護」です。
言い換えれば、ADLのみを考える介護から脱却するということです。
人は「風呂に入る」「トイレに行く」ために生きているわけではありません。
ADLは重要ですが、あくまでも生きる手段であって目的ではありません。
本人の生活・人生を豊かにする視点での介護が必要です。
介護職・看護職・保育士の3%賃上げへ
政府が11月19日(金)に決定する経済対策の主要項目が11月11日(木)に判明しました。
介護職、保育士、看護職の賃金を約3%程度(約9千円)引き上げる方針です。
2022年2月から9月分は補正予算の交付金で確保する予定。
申請の手続きなどがあるため、手元に届くのは来春以降になる見通しとなっています。
2022年10月以降は介護報酬や診療報酬で対応していく。
看護師の給与は全産業平均より高いため、「救急医療体制を担う医療機関に勤務」の条件が付く予定となっています。
口腔ケアの目的と分類
口は「食べる、話す」などの重要な役割を担う器官であり、口の健康は全身の健康につながっています。
老化や病気の後遺症などで口腔の機能が損なわれると、嚥下や誤嚥性肺炎などのリスクが高まるだけでなく、食べたり話したりする行為が困難となり、生きる喜びを失ってしまいます。
口腔ケアを行うことで、摂食機能の維持・向上、虫歯・歯周病の予防、誤嚥性肺炎の予防、唾液分泌の促進、発語・発声によるコミュニケーション機能の維持・向上など、さまざまな効果が見込めます。
口腔ケアは、口腔内の歯や粘膜、舌などの汚れを取り除く「口腔清掃(器質的口腔ケア)」と、口腔機能の維持・向上を目的とした訓練を行う「口腔機能訓練(機能的口腔ケア)」に分けられており、この2つを組み合わせることでケアの効果がさらに高まります。
ご利用者の状態に合わせて、口腔機能向上のケアと訓練を行いましょう。
【保険外サービスについて】移送サービス
公共交通機関やタクシーなどが使えず、ちょっとした買い物や通院などの日常的な移動や外出に困難を感じている方は多くいます。
そのような方に対し、利用者宅から目的地まで、基本的には「ドア・ツー・ドア」で移動や外出を支援するのが「移送(移動/送迎)サービス」です。
最近では、地域包括ケアの一環として、市民グループや非営利団体がボランティアとして行うものや、介護事業所の送迎車を活用(送迎を行わない時間帯の車両・人材を活用)したサービスなども増えています。
介護報酬改定に伴う基本報酬の0.1%特例は9月30日(木)終了
厚生労働省は2021年9月28日(火)に「感染防止策の継続支援」の周知についてを発出しました。
この特例は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた令和3年度の介護報酬の特例的な評価として、令和3年9月末までを期限に4月より基本報酬に0.1%上乗せということで始まりました。
10月以降については、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することとされており、今回の「感染防止策の継続支援」という形に落ち着きました。