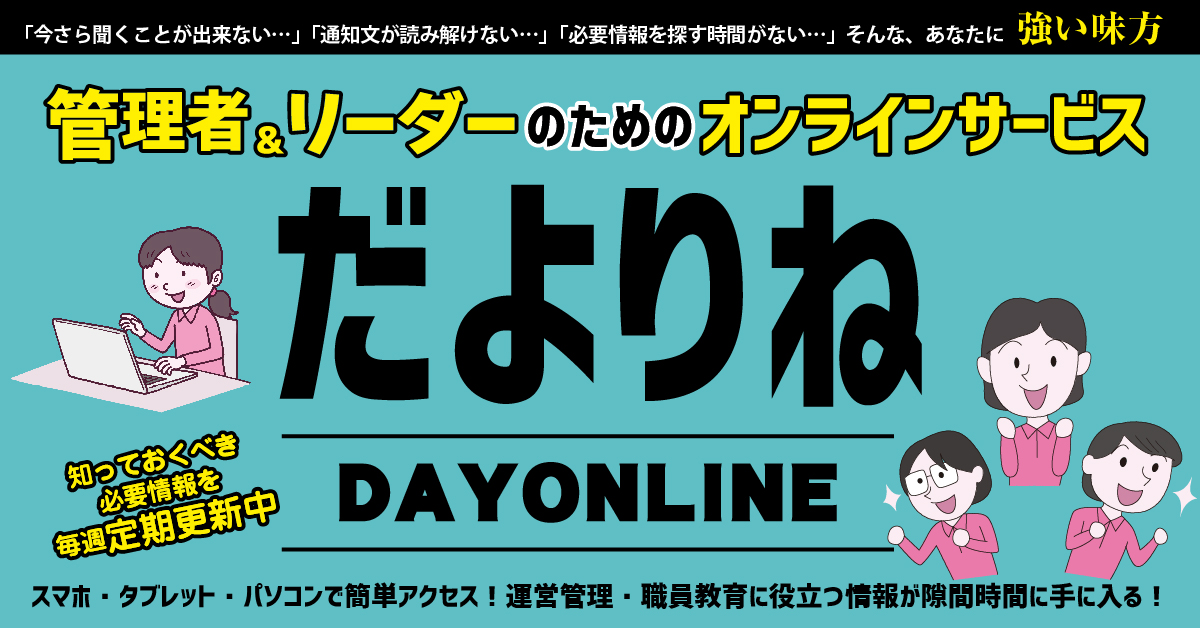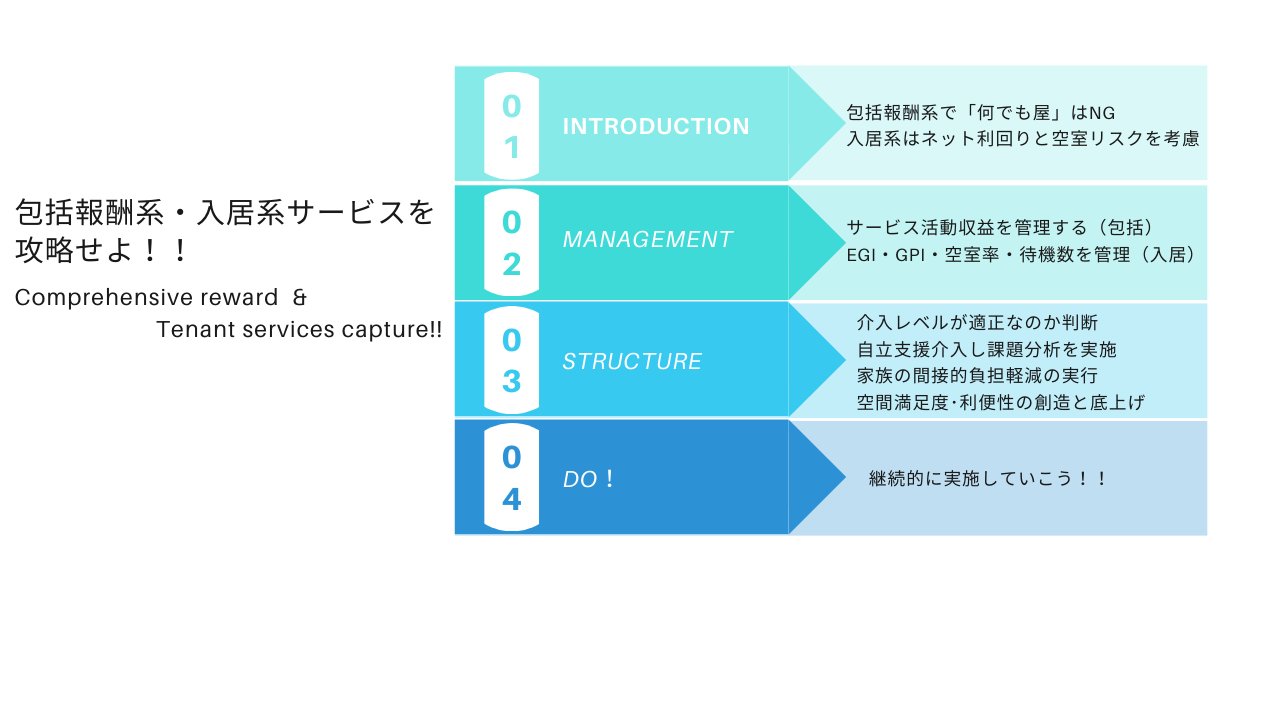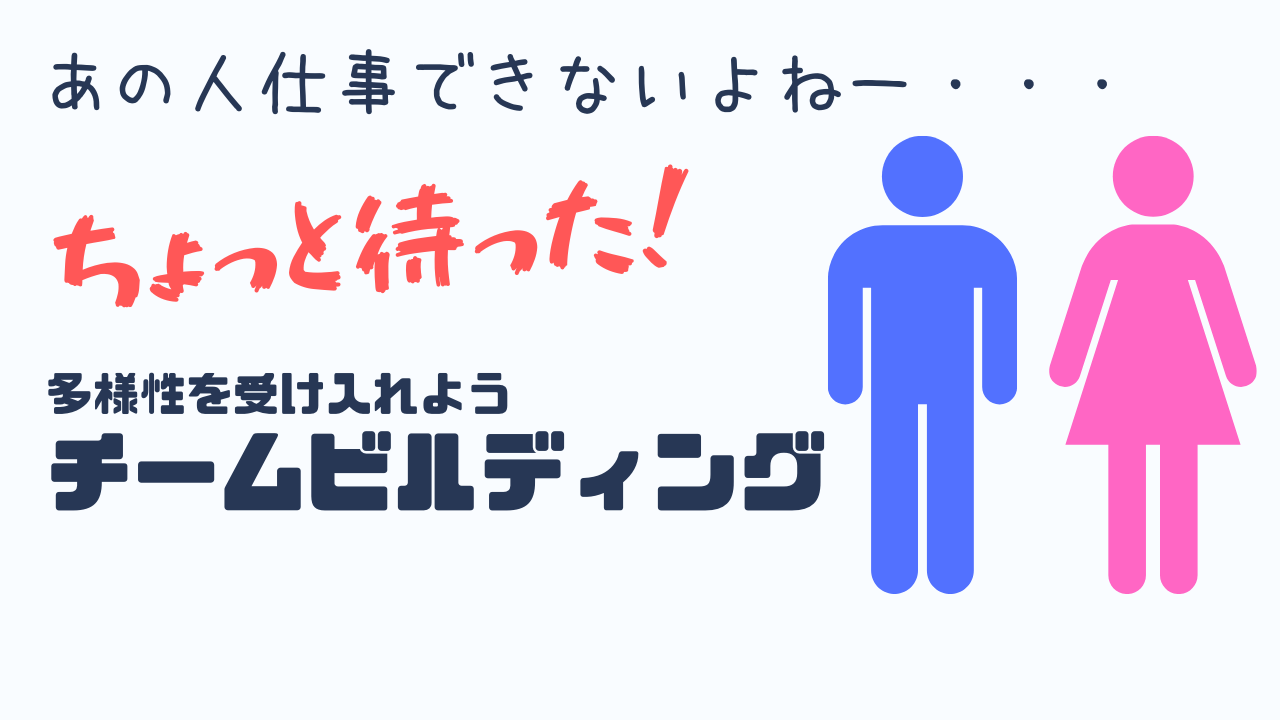【利用者を増やす㊙営業術】第30回 ケアマネにペコペコしている事業所は人気出ません
ケアマネさんにペコペコしていても稼働率なんて上がりません

みなさんこんにちは株式会社QOLサービスの相田です。
今回の内容はちょっと刺激的ですが、本質的な内容なので最後まで必ず読んで頂きたいと思います。
みなさんケアマネさんにペコペコしていませんか?
これ、今すぐ辞めた方が良いです。別に、管理者や生活相談員がペコペコしていることが稼働率に繋がることなんて
ありませんから。
勘違いして欲しくないのが、相手を不快にさせるようなことをして下さいと言っている訳ではないですからね?
あくまでも社会人として当たり前の関わり方はしますが、ケアマネさんの何でも言う通りに仕事をしていてはダメだと
いうことです。
皆さんは誰にサービスを提供していますか?誰のために日々仕事をしていますか?
答えは簡単だと思いますが、もちろん目の前にいるご利用者のためですよね。
つまり、皆さんが一番に考えなければいけないのは「ご利用者」のことです。
そして、デイサービスであれば介護基盤を支えるご家族の状態に気を配ることも大切です。
ただし、ご家族を一番に考えるのではありません。ご家族に気を配りながら「ご利用者」のことを1番に考えるんです。
この本質を理解している人と、理解していない人では、営業時の行動に大きな差が生まれてきます。
さらに、ご利用者のポジションについても勘違いをしている人が多いです。
「◯◯さんは認知症じゃけ~言っても分からない」
「◯◯さんは認知症じゃけ~ご家族とお話せんといけん」
これ、とんでもない大間違いですよ。
担当者会議や、居宅訪問してサービスの提案をする際にご利用者の表情を見てみてください。
「ご利用者をのけ者にするように話をしている時、ご利用者は憤っていますよ」
動けないので、感知し辛いかもしれませんが、微妙な表情の変化に気を配るよう意識してみてください。
ご利用者は、担当者が「自分についてどのように考えているか」しっかり聞いてます。
そして、内容は覚えていないかもしれませんが、その時のあなたの雰囲気はご利用者の中に残っています。
そんな調整をした後に、ご利用者が長くデイを利用して下さると思いますか?答えは否です。
当たり前のことですが、お客様の理解をしなくてはいけません。
認知症の方は、覚えることや理性を利かせたりすることが苦手なだけで、私たちと何も変わりません。
というか、人生の先輩です。
みなさん、サッカー部に所属していて、先輩が骨折したらタメ口になるんですか?
なりませんよね。
だから、尊厳を保持して、丁寧に寄り添って接することが大切なんです。
迷惑なマインドを持ったボランティアさんと一緒で、別にあなたに頼んでないのに「やってやってる」という気持ちを持たれても
迷惑ですし、お金をしっかりお支払いしている訳ですから、ちゃんと仕事として取り組まなければいけません。
冒頭でマシンガントークしてしまいましたが、伝えたかったのは
「ご利用者のことを一番に考えた最善の選択」を実施して欲しいということです。
今回の記事では、事例を交えながら、ご利用者から信頼される関りとは何なのか。
介護疲れが発生しているご家族が、介護を勉強して少しでも前向きに考えて下さるようになる関わりとは何なのか。
稼働率を上げるためには、ケアマネさんとどのように関わるべきなのか。
この3点について深堀していきますので、ぜひ最後まで読んで頂きたいと思います。
そして、明日から必ず実践をして頂きたいと思います。