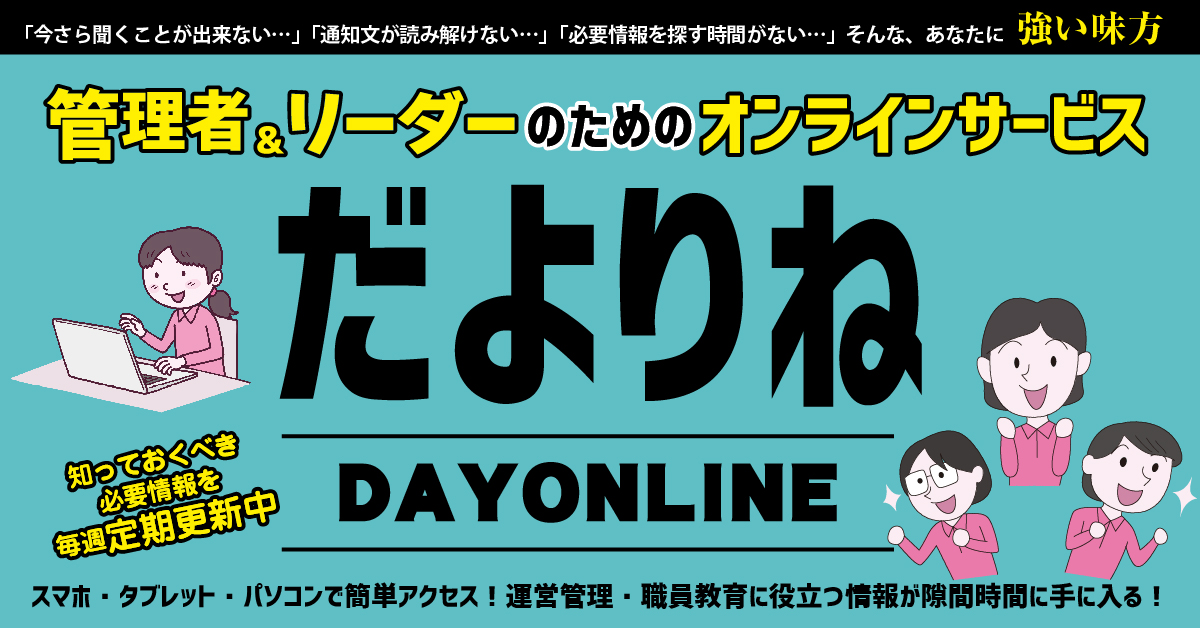【サービスの質向上】各症状に応じた認知症ケア(脳血管性認知症)
各症状に応じたケアをする
脳血管性認知症には、多発性梗塞性認知症、脳出血性血管性認知症、多発性ラクナ梗塞認知症、進行性皮質下血管性認知症(ビンスワンガー病)、低灌流性血管性認知症などさまざまなものがあり、かつ、障害部位によって発生する症状もさまざまとなります。
したがって、本人の症状を細やかに観察し、おかしいと思うところがあれば、お互いに情報交換し、症状把握に努めることが大切となります。
また、他の認知症に比べ、脳血管障害の再発リスクも高いので、脳血管障害の発生リスクを低下させる働きかけも重要となります。
<ポイント>
(1)多彩な症候群の総称であり、障害部位により症状はさまざまとなる
(2)出現している症状に合わせたケアが重要
(3)脳血管障害の再発リスクを軽減させることが大切
【サービスの質向上】各症状に応じた認知症ケア(アルツハイマー型認知症)
認知症にはアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症などがあり、それぞれ症状が異なるため、各認知症の種別を考慮しケアをする必要があります。
(1) アルツハイマー型認知症
記憶障害、見当識障害、取り繕い反応、被害妄想、感情障害(うつ→多幸)、言語障害
(2) 脳血管性認知症
多発性梗塞性認知症、脳出血性血管性認知症、多発性ラクナ梗塞認知症、進行性皮質下血管性認知症(ビンスワンガー病)、低灌流性血管性認知症などがあり、それぞれの障害部位によって発生する症状もさまざま
(3) レビー小体型認知症
認知機能の変動、幻視、誤認、妄想、パーキンソニズムによる歩行障害、日中の眠気
(4) 前頭側頭葉変性症
常同行動(常同的周遊、時刻表的生活、常同的食行動異常など)、脱抑制(周囲の迷惑を顧みず自分がしたいことをする)。
・前頭側頭型認知症(前頭型ピック病など)
・進行性非流ちょう性失語
・意味性認知症【側頭型ピック病など】
(5) その他
65歳以上の方での発症率は、アルツハイマー型認知症 3%、脳血管性認知症 3%、レビー小体型認知症 1%、前頭側頭葉変性症 1%です。
(この他の数値を示す研究もあります)
【基準・算定要件Q&A】個別機能訓練加算
個別機能訓練加算の在り方は、実務の手順が厚生労働省から示されています。
また、令和3年度から新設された(Ⅱ)は、LIFEを用いたデータ提出が求められています。
■個別機能訓練加算
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ…56単位/1日につき
・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ…85単位/1日につき
・個別機能訓練加算(Ⅱ)…20単位/1月につき
【基準・算定要件Q&A】生活機能向上連携加算
生活機能向上連携加算は、外部の理学療法士などと連携し、利用者の身体状況の確認、個別機能訓練計画の作成などをした場合に算定します。
■生活機能向上連携加算
・生活機能向上連携加算(Ⅰ)…100単位/1月につき(※3月に1回を限度)
・生活機能向上連携加算(Ⅱ)…200単位/1月につき(※個別機能訓練加算を算定している場合、100単位/1月につき)
【基準・算定要件Q&A】中重度者ケア体制加算
中重度者ケア体制加算は、利用者総数のうち、要介護3以上の利用者が一定の割合を超えていること、サービス提供時間帯を通じて専従の看護師を配置し、人員基準で求められている介護職員または看護職員の員数に加えて、常勤換算で2以上を配置することなどが求められます。
■中重度者ケア体制加算
45単位/1日につき
【基準・算定要件Q&A】入浴介助加算のおさらい
入浴介助加算は、令和3年度介護報酬改定で自立支援の入浴介助を評価する(Ⅱ)が新設されました。
(Ⅱ)の算定に当たっては、居宅を訪問した上で入浴環境や動作を確認・評価し、それに基づいて自立支援の環境設定や介助方法などを決定する必要があります。
■入浴介助加算
・入浴介助加算(Ⅰ)…40単位/1日につき
・入浴介助加算(Ⅱ)…55単位/1日につき
※通所リハは60単位
【基準・算定要件Q&A】延長加算
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話をした場合に、5時間を限度として算定される。
■延長加算
・9時間以上10時間未満…50単位/回
・10時間以上11時間未満…100単位/回
・11時間以上12時間未満…150単位/回
・12時間以上13時間未満…200単位/回
・13時間以上14時間未満…250単位/回
【サービスの質向上】「課題解決型アプローチ」と「目標指向型アプローチ」
介護で中心となるのは「目標指向型アプローチ」
アプローチの方法には、本人が抱える問題点を探し出し、その問題点を課題としてとらえ解決することで、元の状態・より良い状態にしようとする「課題解決型アプローチ」があります。
課題解決型アプローチは、急性期医療でよく使用される考え方です。このアプローチで重要なことは「課題」が解決できることです。
解決できない課題の場合はこの手法は取れません。
課題解決型の視点でアプローチする例としては、生活不活発症候群(旧・廃用症候群)としての筋力低下に対して筋トレを実施したり、認知症のBPSD[認知症の行動と心理症状](旧・問題行動)を解消・改善したりすることが挙げられます。
一方、ある目標を設定し、その目標を達成することで、より良い状態をつくろうとする「目標指向型アプローチ」もあります。
介護では、高齢者の加齢現象や脳卒中の後遺症などの障害を対象とすることが多く、これらの現象・障害は「解決できない課題」であることがほとんどです。
したがって、介護では課題解決型アプローチを併用しつつ目標指向型アプローチを中心にして進めます。
【サービスの質向上】自己選択の支援
選択肢の設定
自己選択の支援で必要なことは、選択肢を設けることです。
選択肢がなければ、「選ぶ」という行為は不可能になるからです。
「自立支援」の第一歩として、さまざまな場面に選択肢を設定しましょう。
選択は、「その人らしさ」の支援にも必要
現在の私たちがあるのは、過去のさまざまな選択の積み重ねの結果です。
その人らしい服装、その人らしい髪形など、無限にある選択肢・可能性の中から、その都度選択してきた結果が今の自分であり、自分らしさになっています。
「その人らしさ」を支援するためにも選択肢は必須となります。
【サービスの質向上】目標が不適切だと介護そのものが不適切になる
介護は、ケアプランに沿って提供され、ケアプランには、「目標」と「目標を達成するために実施すること」などが記載されます。
目標の内容が変われば、提供されるケアも変わり、本人の人生も変化することになります。
目標が不適切だとケアプランも不適切となり、それを基に実施されるケアは不適切なものになってしまいます。
【ポイント】
・ケアはケアプランに基づいて実施される
・ケアプランには「目標」と「目標を達成するために実施すること」などを記載する
・「目標」が変われば「目標を達成するために実施すること」も変わる
・「目標」が不適切だと、「目標を達成するために実施すること」も不適切になる=ケアプランが不適切になる
・ケアプランが不適切だと、それに基づいて行われる日々のケアは不適切なものになってしまう