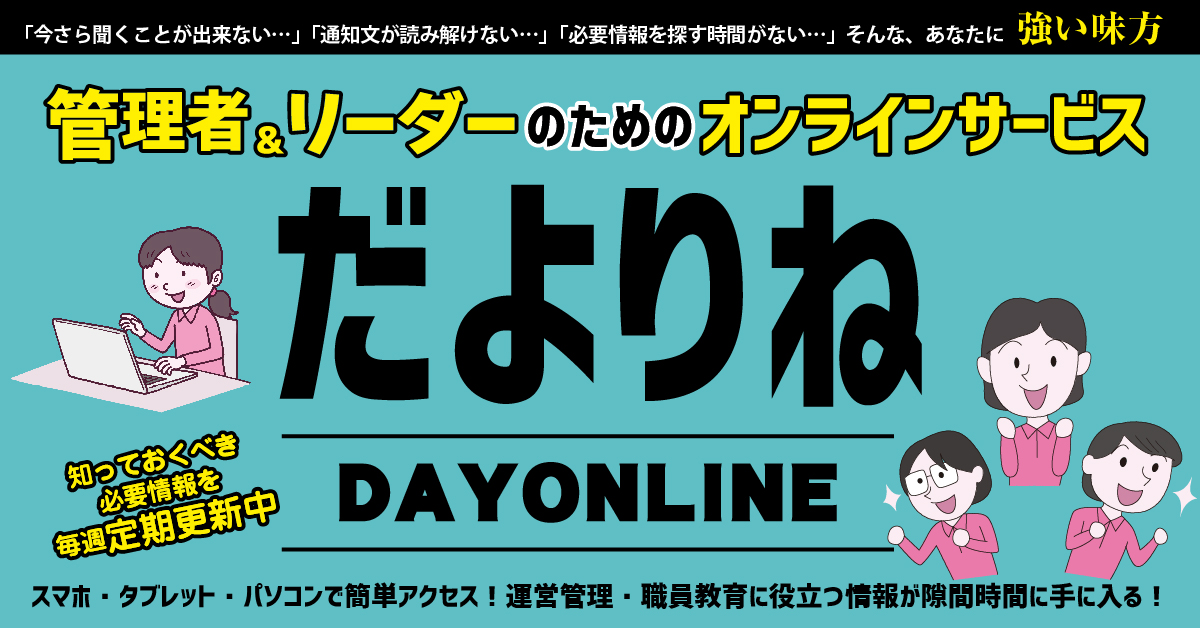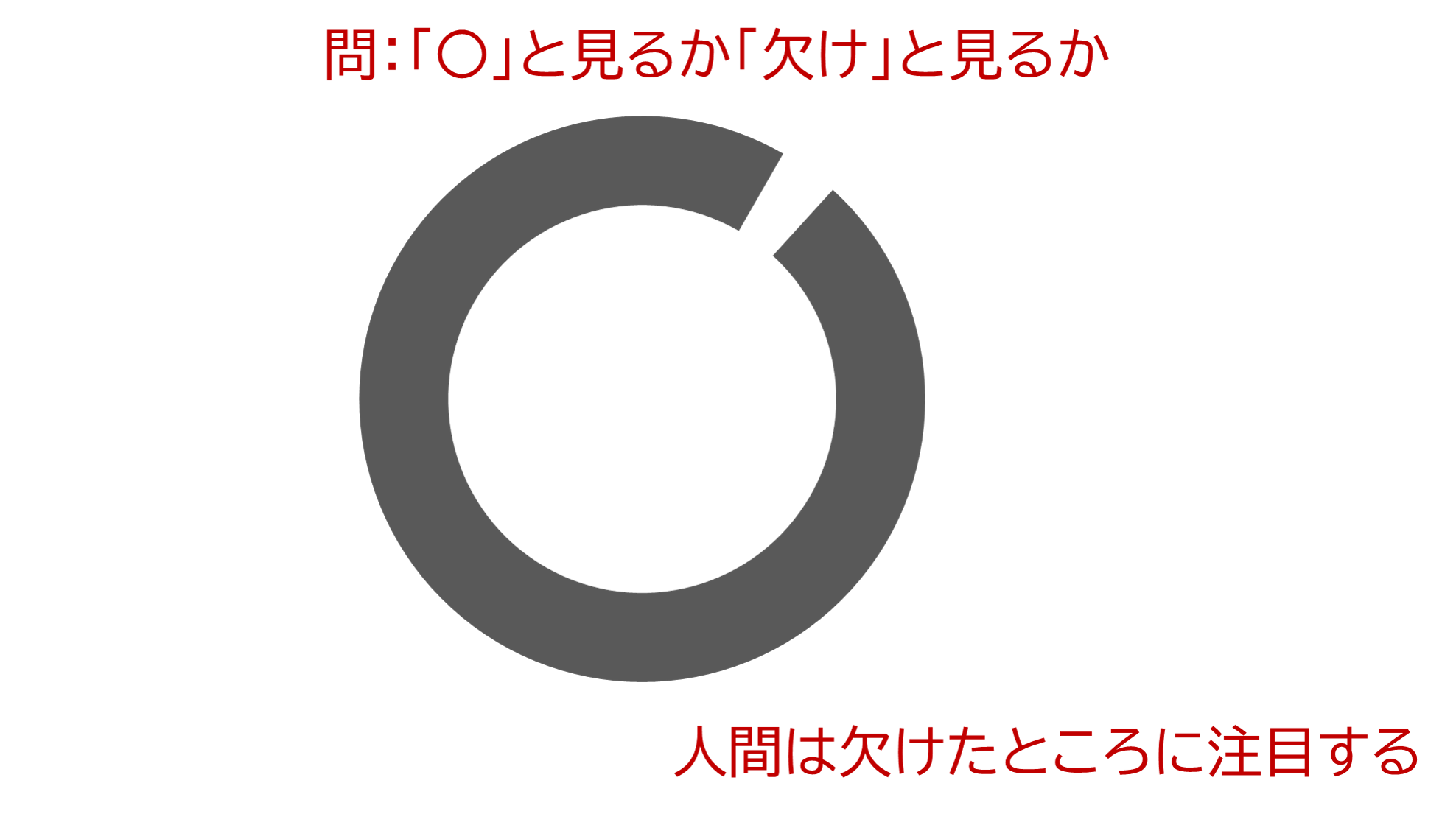【利用者を増やす㊙営業術】第31回 連絡を取りたくなくなる担当者は◯◯が遅い
連絡を取りたくないと思わせる人の特徴

みなさんも、「この人とはもう連絡取りたくないな(汗)」って思った人いませんか?
・否定的思考な人
・自己中心的な思考である人
・自責ではなく他責(人のせいにしているのが伝わる)である人
・イライラしていたり忙しそうな人
など、色々な理由があると思いますが、もう1つ見落としてはいけない「重要な理由」があります。
それは・・・
レスポンスが遅いことです!
これは、相手のことを非常にイラつかせることができてしまうので危険ですから(笑)
しっかり学んで頂きたいです。
レスポンスは、日本語で「応答・返信」と訳されるため、レスポンスが遅いということは
連絡や返信が遅いということになります。
じゃあ、連絡や返信が速ければ良いのか!!と言われると、それもダメです(は?って思いますよね笑)。
レスポンスが遅いという「遅い」とは
単に、連絡や返信のスピードの「速さ」に対してではありません。
相手のタイミングに対して「遅い」= レスポンスが遅い
レスポンスの速さ基準は、一般的な「スピード(速さ)」でも担当者の思う「速さ」でもなく
相手が心地よく感じる「速さ」であり、レスポンスが速い人というのは
ちょうど情報を欲している時や、そろそろ気になり始めるちょっと前にタイミングよく連絡してくれるんです
重要なのはタイミングであり、相手とのスピード感です。
2人3脚を想像してみてください!!
2人のタイミングがピッタリ揃っていないと転げてしまいますよね?
速すぎても、遅すぎてもダメで、相手の速さに合わせてあげることが大切なんです。
今回の記事では、この「レスポンスを合わせるコツ」について紹介をしていきます。
なかなか相手のペースを理解することは難しいと思いますので、今回の記事で"コツ"を学んで
実際の現場で活用してみてください!
使う人は誰でもOKです!ご家族、友達、取引先、ご利用者、ご家族、ケアマネ、誰にでも応用できますし、
きっとこれが身に付いていれば、相手が好意を持ってくれることも増えていくと思います!
ぜひ、最後まで見て頂けると嬉しいです👍
【サービスの質向上】更衣・整容での環境設定の工夫
更衣・整容は生活のスタートです。
出掛けるとき、帰宅後、就寝前など、次の行動のために身なりを整えます。 しかし、認知症になり、更衣の一部の動作を忘れてしまうと服が着られなくなり、次の行動にも支障が出ます。
外出するための服に着替えられないから外出ができない、したくない。
就寝着に着替えられないから寝たくてもその気分になれない…。
こうやって考えると、更衣・整容と行動には密接な関係があります。
そのため、認知症になってもなるべくひとりで、もしくは最小限の支援で更衣・整容を行えることが大切なのです。
ニュースピックアップ[2021年7月11日(日)~17日(土)]
2021年7月11日(日)~17日(土)の各業界のニュースをピックアップし、月刊デイ編集長である妹尾弘幸氏(株式会社QOLサービス 代表取締役)が介護の視点から言及いたします。
【1】最低賃金額28円増で平均930円へ
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は7月14日、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、時給930円とすると決めた。
この引き上げ額は過去最大となり、上げ幅は3.1%となる。
ニュースピックアップ[2021年7月2日(金)~10日(土)]
2021年7月2日(金)~10日(土)の各業界のニュースをピックアップし、月刊デイ編集長である妹尾弘幸氏(株式会社QOLサービス 代表取締役)が介護の視点から言及いたします。
【1】年金運用、黒字額約37兆円
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2020年度の運用損益が過去最大の37兆7986億円の黒字だったと発表しました。
黒字となるのは2年ぶり。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた、主要国の金融緩和や大規模な財政出動で国内外の株価が大幅に上昇したことが運用益を押し上げました。
2019年度の運用損益はコロナ禍に伴う株安で、過去2番目に大きい赤字に陥りましたが、一転して改善。
これまで黒字額が最大だった2014年度の15兆2922億円を大幅に上回りました。
2021年3月末時点の運用資産額は186兆1624億円。
市場運用を始めた2001年度からの累積収益額は95兆3363億円に上り、いずれも過去最大を更新しました。
【サービスの質向上】入浴での環境設定の工夫
入浴は、一番安らぐ時間でありたいものです。そのためには、入浴時にどのように過ごしてもらいたいのか、どのようにしていくことが必要なのかを考えないといけません。
入浴時は通常のフロアなどでの状況と違って、衣服がなく無防備な状態です。
その点を理解しながら環境設定を考えます。
介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額、高額介護サービス費の負担限度が見直しとなります!
2021年8月から介護費用の「食費負担金額」が変わる人が出てきます。(第2段階、第3段階の方)
特にショートステイでの食費負担金額が変わる人が多いので、デイの利用者でショートステイを利用しているご利用者にも周知をしてください。
<2021年8月1日からのショートの1日の食費負担限度額>
【1】年金収入等が、80万円以下の方(第2段階):390円 → 600円
【2】年金収入等が、80万円超え~120万円以下の方(第3段階[1]):650円 → 1,000円
【3】年金収入等が、120万円超え(第3段階[2]):650円 → 1,300円
施設入所の方は、120万円超え(第3段階[2])のみ650円 → 1,300円への改定となります。
なお年金収入等での「預貯金額」の認定要件も変化しています。
【介護の職場の課題】職員不足
職員の高齢化
介護労働安定センターの平成30年度介護労働実態調査結果によると、介護職員の平均年齢は、全体で 47.7歳で、訪問介護員の平均年齢は 54.3歳でした。
訪問介護員は、70歳以上が10.5%、65歳以上が1/4を占めます(下図参照)。
介護保険が中重度中心になっていくと、身体介護の割合が増加するため、高齢のヘルパーでは、対応が困難となってくる恐れがあります。
近い将来、1/4を占めるヘルパーが退職したとき訪問介護は存続可能なのでしょうか。
65歳の職員は、5年後に70歳になり、1/4の職員は70歳以上になります。
年々、60歳以上の職員割合が増加しています。
この状態が続いて将来、介護サービスの提供は可能でしょうか。
【離職防止A to Z】「次はやろう!」と思ってもらえる伝え方
ネガティブな言葉よりもポジティブな言葉の方が、相手の好ましい行動を導きやすいと言われています。
さらにこれに加えて「伝える際の語順」にも気を配ることをでより好ましい行動に導くことができます。
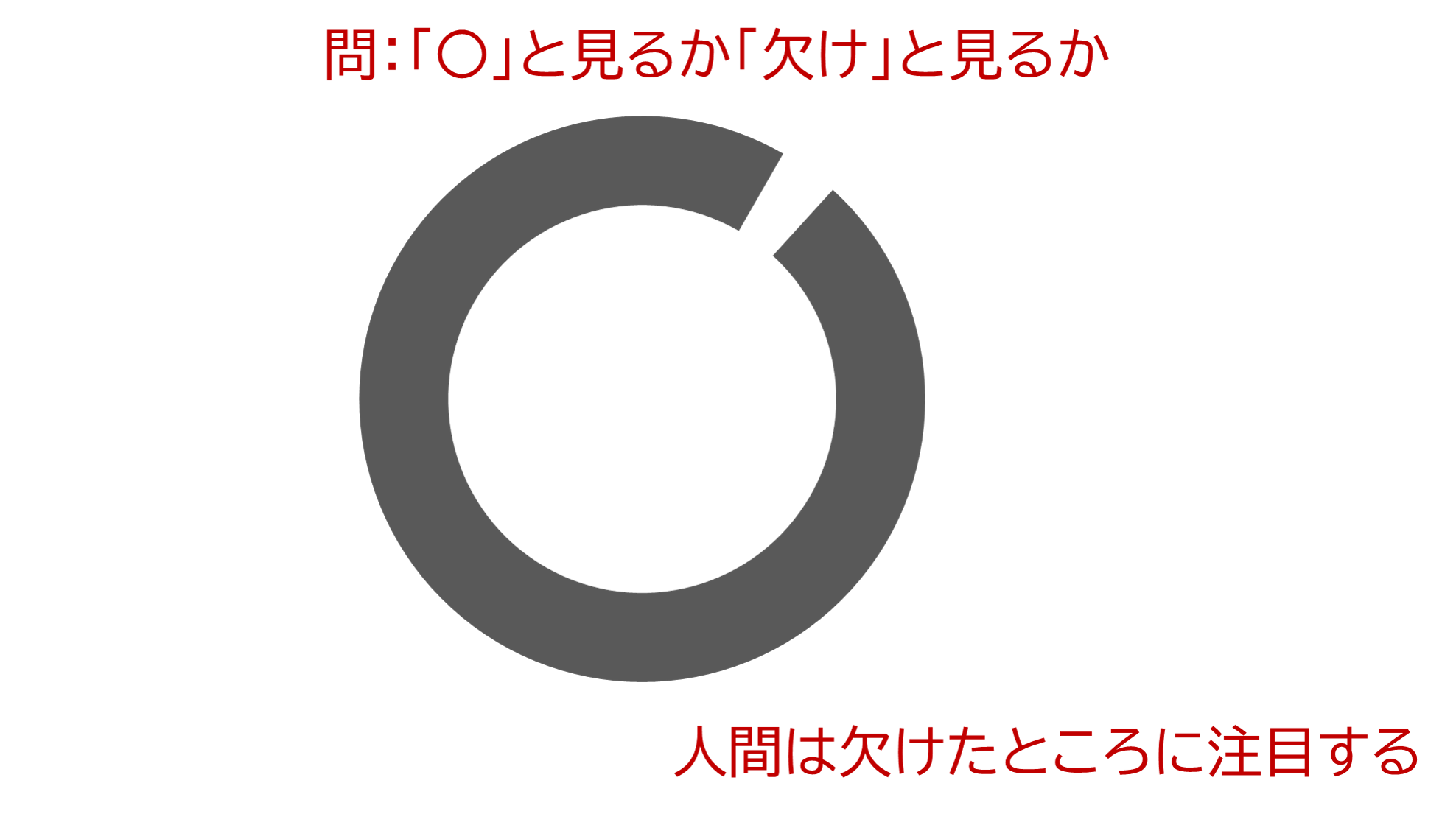
突然ですが、みなさんは上の図を目にした時、最初にどこに注意がいきますか?
おそらく多くの方が、「これは線がつながっていないから〇ではない」のように、円の欠けている部分に注目するのではないでしょうか?
人間の心理は自ずと「完全な」円を求め、欠けた部分に着目し「まん丸だったらいいのに…」と望みます。
では、こうした心理状態を人間関係や教育・指導に当てはめて考えるとどうなるでしょうか。
相手の心に響かせるための「伝え方の語順」、「〇(長所)」を見るか「欠け(短所)」を見るかについてお伝えします。
【サービスの質向上】排泄の環境設定の工夫
排泄において大切なことは、その方が認知症であっても意思、感情はあり、他人の介助を受けることは原則好まないということです。
排泄介助に関しては、早さ、効率、方法に考え方が偏り、肝心の利用者の気持ちへの配慮が後回しになりがちです。
人は納得したときに、その身を任せることができるため、利用者の根底にある気持ちを理解して、排泄介助に納得していただけるような工夫をしなければなりません。
ベッド上での排泄に関しては、ケア、やり方などが重要となりますが、ここではトイレの環境設定の工夫についてお伝えしたいと思います。
【離職防止A to Z】部下の心に響く魔法の言葉「ペップトーク」
ペップトークとは、簡単に言うと「人を励ますための言葉がけ」です。
「ペップ」には、元気や活気という意味があります。
アメリカ発祥のもので、もともとはスポーツの試合前に監督が選手を励ますためにかけたトークのことです。
人間は言葉で考え、言葉で意思を伝える動物です。
ですから、相手のやる気を引き出したり、その逆につぶしたりするのも、言葉が引き金になることが多いものです。
部下に対する言葉がけを工夫することで、やる気が見られなかった部下が、自分の目指すべきことに気づいてイキイキと働き始めたら、上司としても嬉しいですよね。
そのような「魔法の言葉」を身につけるためには、肯定的な短い言葉でわかりやすく表現する「ペップトーク」が有効です。
ぜひ、試しに1つか2つフレーズを使ってみて、明日からの職場の人間関係に役立ててください。
【ペップトークの4つのステップ】

【受容】相手の気持ちや相手が置かれている立場を受け入れる
【承認】相手が「できているところ」を認め、捉え方を変換する
【行動】相手に「してほしいこと」を伝える
【激励】相手の背中を押す