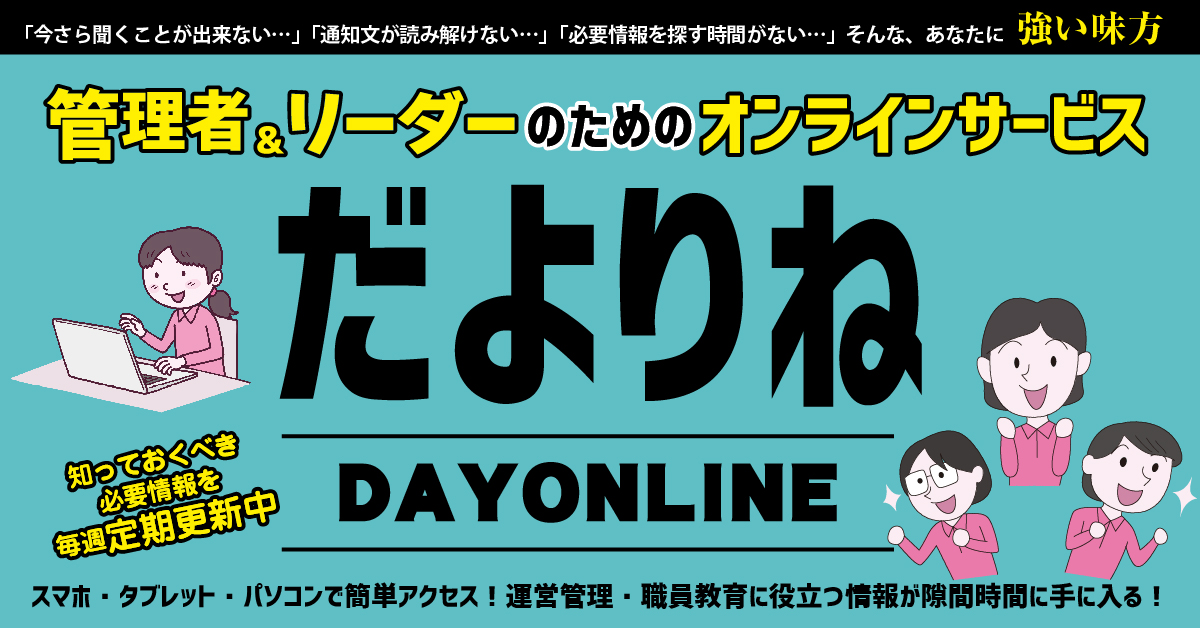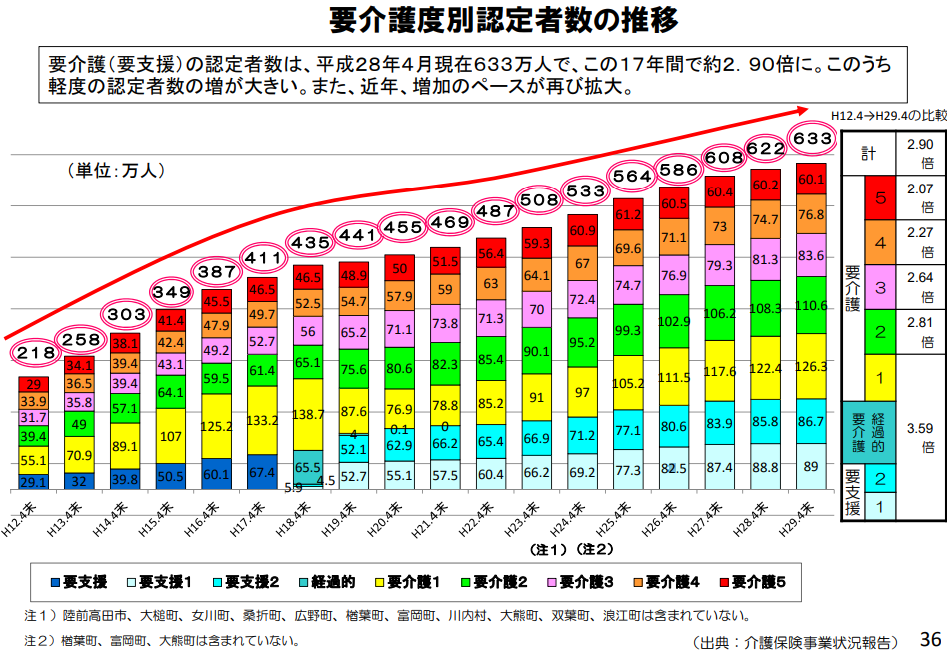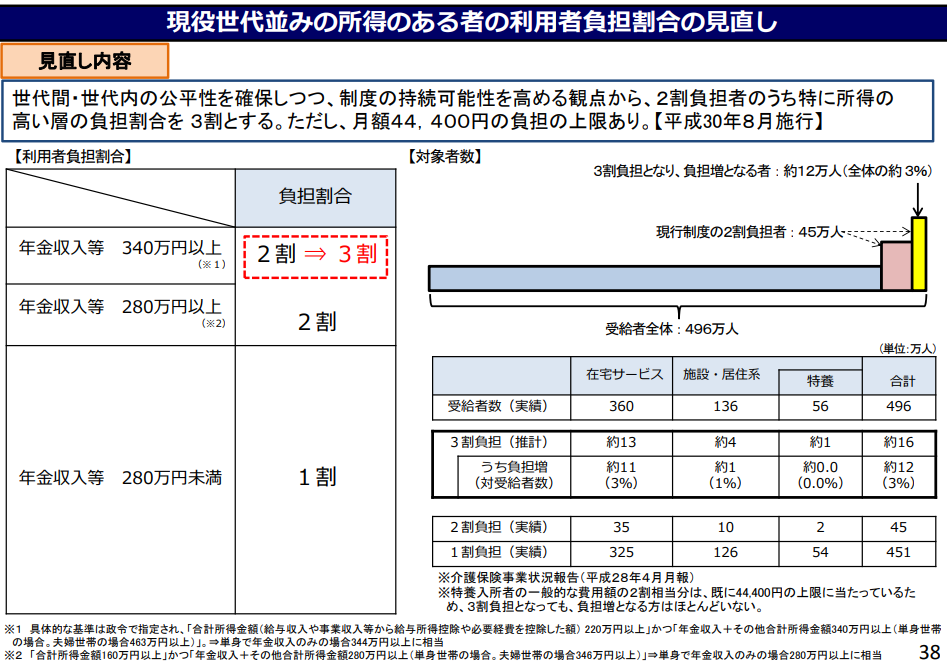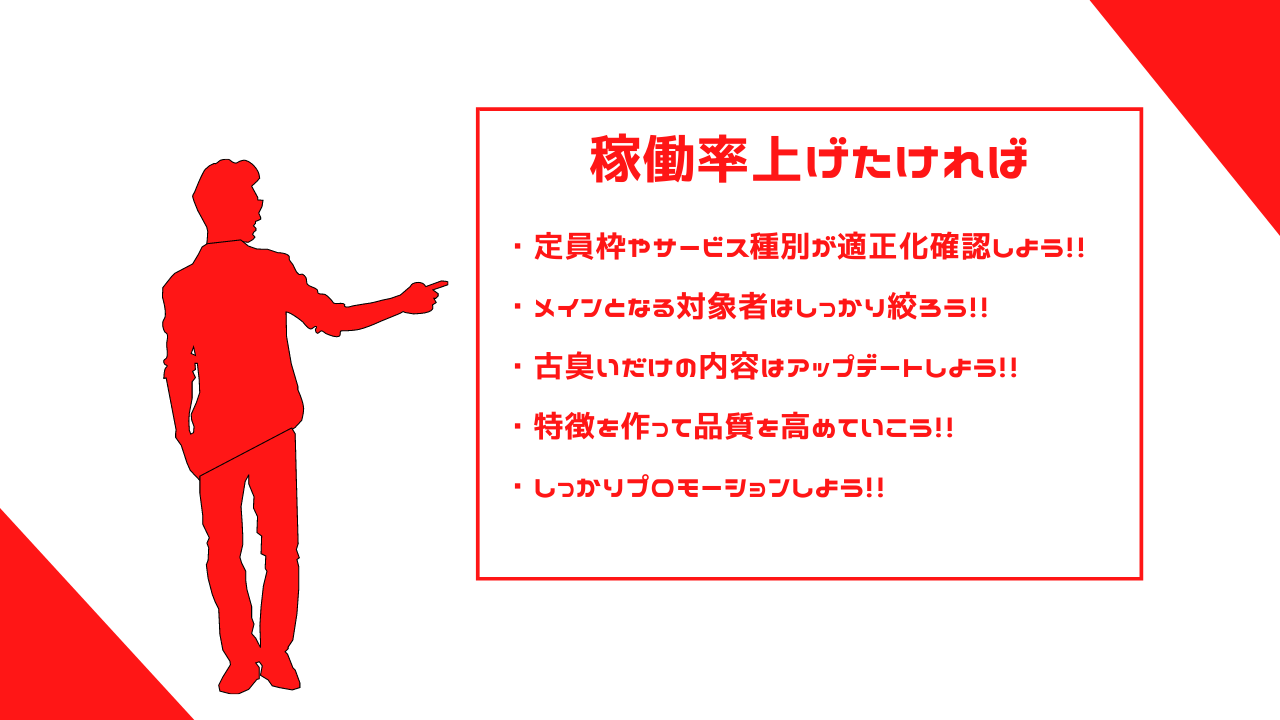皆さん支援の方を簡単に断っていませんか?【運営が難しくなっていきます】

「支援のご利用者は何回来ても売上が決まっているから、週1回利用で月に4枠も取られちゃたまんない!」
と、支援の方を抑えていませんか?
もちろん!支援の枠が要介護1稼働だった場合2倍以上の売上が上がりますから、運営的にも同じ負担をかけるなら
後者を優先して支援利用はできるだけ減らしていく姿勢の方が合理的かもしれません・・・
しかし!それをやり過ぎると・・・「包括から嫌われます(笑)」
包括は、民間ではなく"市町村が設置主体"(直営3割、委託7割)であり、制度横断的な支援を実施している機関である
ため、事業所商圏エリアのフロントサービスなわけです(介護保険サービスの入口的存在)。
すなわち、"顔が広い"し"介護保険に関する相談が多方面からたくさん来ます"。
そこに嫌われるということは、"事業所の評判の悪さも伝搬します"し、"支援や介護の相談が無くなってしまい
ます"。
すなわち、新規利用者の獲得数は落ちていきます。
また、包括だけ断って、別居宅からの支援相談を受けようとしても、直系の包括チェーンとなっているため、
「私からは断ったのに、なぜあの居宅からは受けるの?」と疑問視されてしまいます。
つまり、商圏全体での動きが重くなってしまうんです(それ以前に、基本的に断れないはずなんですが・・・)。
商圏全体の動きの重さは深刻で、ケアプランに沿った保険サービスを提供するといった構造上、ケアマネの絶対値に
商圏内利用者数は依存することになります。
それなのにも関わらず、商圏内の保険サービスは飽和しており(事業所も多いし、需要が高くても人員不足というトレード
オフで受けれない)、ケアマネも担当件数が実態的に35件~40件程度となるので、紹介が受けられる利用者数も限られま
す。また、集中減算80%というラインを考慮すると、1人当たりのケアマネから紹介を受けられる件数上限は20%となり、
7件~8件程度となります(もちろん委託型の包括も自事業所への紹介はします)。
商圏内のケアマネ事業所が200件、1事業所当たり3名のケアマネが在籍しているとすると、商圏内紹介上限は120名
となり、それを商圏内の介護事業所で取り合うことになるので、激戦となる訳です※。
※別の記事でも書いていますが、あなたの事業所に利用調整の相談が来ることは奇跡です。
すなわち、商圏内の居宅だけに集客リソースを割いていると事故ります。
上手く運営出来ている事業所は必ず包括と良好な関係性を築いているんです。
包括は、1人ひとりの相談員に対して担当上限が設けられていません。
つまり、青天井であるわけです。
自分でもプランを作成して対応しますが、物理的に限界があるため、居宅を含む地域資源に斡旋して対応しているのが現状
であり、地域の介護保険サービス構造上でいうと、インサイドセールス的なポジションであるわけですから、
大きな商社であれば、一番売上に直結する重要な部門である訳です。
この集客性を無駄にしてしまう事業所は、限られた地域資源に集客力を限定されてしまうことになるので、必ず利用を
前向きに調整して良好な関係を維持し続けていく必要があります。
また、包括との良好な関係性は加算の取得にも大きな影響を与えることになります。