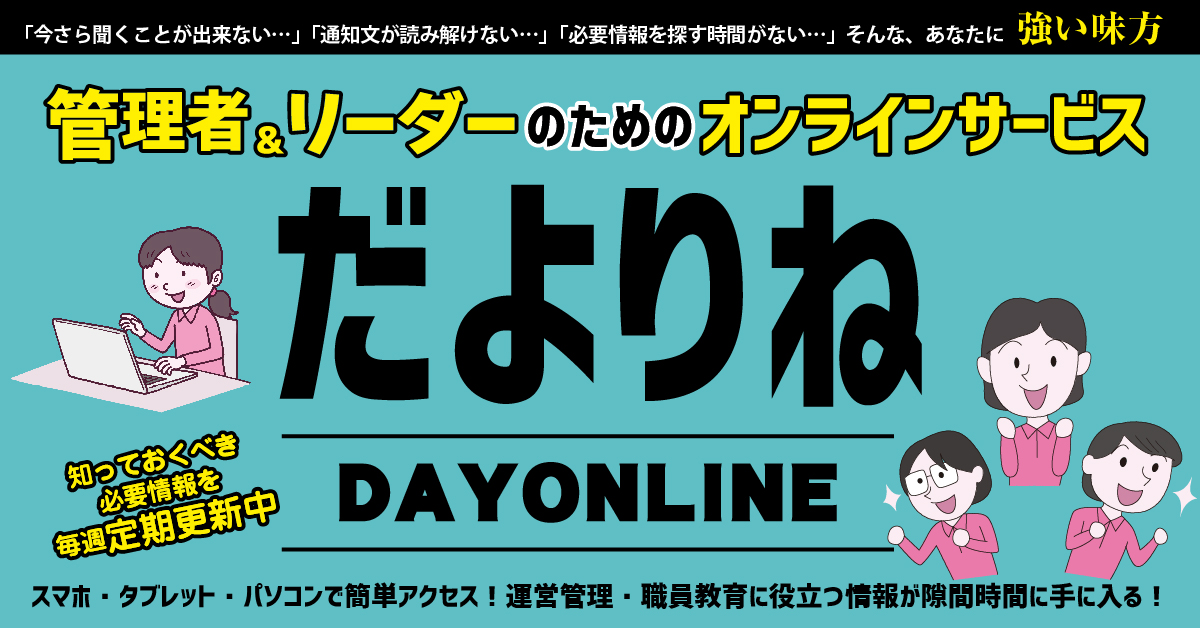【PR・営業ワンポイントアドバイス】相手の情報を鵜呑みにせず自分で確かめる
新規の問合せでケアマネからご利用者の情報をヒアリングした際に、「ウチでは難しいかな?」と感じたことがありませんか?
例えば、「暴言や暴力を振るうことがある」であったり、「拒否が強くて入浴や食事が難しい」、「認知症の症状が進行していて帰宅願望が強い」など、契約に際して担当者レベルで
「うっ・・・大変そうだな」と感じてしまうことは多々あると思います。
それもそのはず、管理者や生活相談員は「まず、現場が回るのか」、「今の職員のスキルで対応できるか」など、自分たちが提供しているサービスレベルが落ちてしまわないか、そもそも対応可能なのかなど、総合的な観点で判断するからです。これ自体は自然で、妥当な判断の仕方だと思うのですが、大きな間違いが1点だけあるのがお分かりでしょうか?
今回の記事では、新規利用の問合せで機会損出をしないための基本的な考え方を学ぶことができる内容となっています。
ぜひ、自事業所の体制を見直すきっかけとしていただけると嬉しいです。
【サービスの質向上】認識力低下に対するケアと環境設定
認識力が低下した方に対する環境設定の考え方
認知症などにより認識力が低下した方に対する環境設定の考え方には、
【1】認識力低下を補完する環境設定
【2】認識力低下を活用する環境設定
の2つがあります。
【デイサービス管理者の仕事の手引き】虐待・身体拘束を防ぐ
介護施設の職員による虐待は増加傾向にあると言われており、その大きな原因として「教育や知識、技術の問題」が挙がっています。
管理者は職員が正しい知識や技術を身に付けられるよう指導する必要があります。
【PR・営業ワンポイントアドバイス】営業結果は「自信」に左右される
介護事業所にも「営業」は存在し、ケアマネや病院からの紹介を獲得し続けていくためには「営業」と向き合う時間が必要です。
私は、医療機器ディーラーとして、地域で最も大きな急性期病院のドクターを相手に新規商材営業を行ってきましたが、どれだけ「営業」をかけても結果が出ない日々を過ごしました。
結果が出始めたのは、あることの重要性に気付いた入社3ヶ月後から。そこからは、先輩社員の新規採用件数をごぼう抜きで抜いていくことになります。
みなさんも、FAXDMを送ったり、HPを更新したり、電話で問い合わせてみたり、パンフレットを持って営業に出かけてみたり、利用者を増やすために色んな手法を実践してこられたと思いますが・・・結果が出なくて悩んでいる方・・・結構いるんじゃないですか?
上手くいっている時は、なぜうまくいっているのか分からない時がありますが、結果が出ない時は明確な原因があります。
今回の記事では、売れていない人の特徴3つに着目したワンポイントアドバイスを行います。
皆さんのPR・営業活動の一助となれば、嬉しいです。
【サービスの質向上】感覚に対するアプローチ
感覚について
認識の基になるさまざまな情報を得るためには、感覚が必要です。
老化や認知症疾患などで感覚機能が低下すると情報の収集に困難を来たし、認識力が低下するので、感覚機能系に対するケアが大切です。
認識力の維持と低下の予防改善には感覚に対するアプローチが重要となります。
【PR・営業ワンポイントアドバイス】営業活動は数字で管理しましょう
皆さんは自事業所に一番紹介して下さっているケアマネさんを答えられますか?
また、地域でケアマネさんが一番いる事業所がどこか、そこから何件の紹介が来ているか答えられますか?
それが答えられて何になるのかと思う方もいると思いますが、営業のムラとムダを無くすには、こういった情報を数字で管理しておくことが
重要なんです。
営業活動は皆さんの事業所で重要な仕事ではありませんし、しなくても利用者が増えるならそれが一番望ましい状態です。
しかし、商圏内の介護事業所が増え、競合が発生している場合は、自事業所のメリットを外部に伝えていく必要が必ずあります。
情報社会の現代では、いくら良いサービスを行っていたとしても、情報に埋もれてしまうだけで機会損失が発生してしまうからです。
ただ、そうは言っても忙しい介護現場を回す中で、どのようにして営業活動したらいいのか分からず悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな皆さんにとっておきの営業管理方法を今回の記事ではお伝えしたいと思います。
【傍聴報告】第95回介護保険部会「介護人材の確保、介護現場の生産性の推進について」
2022年7月25日(月)に、第95回介護保険部会が開催されましたので月刊デイ編集長であり日本通所ケア研究会会長の立場から私感を交え報告します。
2019年度時点で211万人働いている介護職員が2040年には280万人必要となり、現況から約70万人の増加が必要という推計が出ています。
これに対し、
「退職者も含めた人数に就職してもらう必要があり、非常に厳しい」
「高齢の職員が多く若い職員が少ないため、若い職員の確保を重点的に行っていく必要がある」
「将来は労働者の5人に1人が医療・介護従事者となる必要がある」
「介護保険制度を継続していくためには早急な対策が必要」
など様々な意見が多く出ました。
介護福祉士養成学校の入学率が低下し毎年全国で閉校がでているため、
「介護福祉士を取得後に看護学校へ行く道筋を作ったらどうか?」
との意見も出ました。
これについては、看護団体の委員から反対意見が出ましたが、以前厚生労働省でもフィンランドの「ラヒホイタヤ」を参考に、「看護・介護・リハ・保育」などの共通基礎過程を作り、各資格間の移行を容易にする制度構築を計画し、2023年までに実現していくことを目標にしていましたが、相互に共通する科目があまりにも少ないため困難と判断し、頓挫しているのが実情です。
人材確保についてはすでに色々な施策が行われていますが、各委員からは
「それぞれの施策の具体的な効果を明らかにして効果がある施策を実行すること」
「主婦、若者、高齢者など対象別に応じた施策の実施」
を求める意見が出ました。
【PR・営業ワンポイントアドバイス】営業が苦手でも成果が出る3つの大切なこと
営業の仕事なんてしたことないし、ご利用者に関わることが好きでこの道を選んだのに・・・
営業とは疎遠だと思われている介護業界にも"営業"と呼ばれる仕事があるのをご存知でしょうか?
利用者増のために、「ケアマネや病院の地域連携室に自事業所PRする活動」これを介護業界では営業活動と呼んでいます。
そもそも公的サービスなのに、なぜ販促活動ともとれる営業活動をしなければならないのか・・・
その理由は、介護事業所の数が多すぎて情報が埋もれることや、ケアマネージャーや地域連携室の知識量によってご利用者の紹介先に
偏りが出てしまうためです。
どれだけ良いサービスを提供していても、それが人の目に触れていなければ新規利用者は増えませんし、地域のケアマネや地域連携室に
自事業所の情報をアップデートして伝え続けなければ、忘れ去られてしまいます。
だからこそ、認知を目的とした営業活動を介護事業所の管理者は行っているし、行うべきだと思っています。
ただ、そうは言っても「営業」なんてしたことないし、どうすれば良いのかも分からないし、抵抗がある。という管理者様向けに、
これだけしておけば成果に繋がる3つの大切なことをお伝えします。
【デイサービス管理者の仕事の手引き】最低限しなければならないこと
デイサービス運営にかかわる法令を理解する
自治体ごとに異なる条例(ローカルルール)に注意する!
デイサービスを運営するためには、介護保険法や人員・設備及び運営に関する基準・条例などの法令を守らなければなりません。
まずは管理者やリーダーが遵守すべき法令を理解し、徹底することが大切です。
介護保険は地方分権が進められており、国の定めた基準を自治体が地域の実情に応じた独自のルールとして条例に定めることができる権限移譲がなされています。
多くの条例は国の基準に準じていますが、中にはA市で認められることが隣接する市町村では認められないこともあります。
【サービスの質向上】認識力低下と対応例
認識力低下について
認知症では、視覚機能や記銘力、見当識、注意機能の低下など複数の機能の低下により、事物に対する認識力が低下しています。
認識力の低下は、日常生活の自立度低下、転倒などの事故発生リスクの上昇などを招く恐れがあり、ケア上の対応が必要です。
認識力低下の例とそれに対する具体的な対応例を挙げておきます。