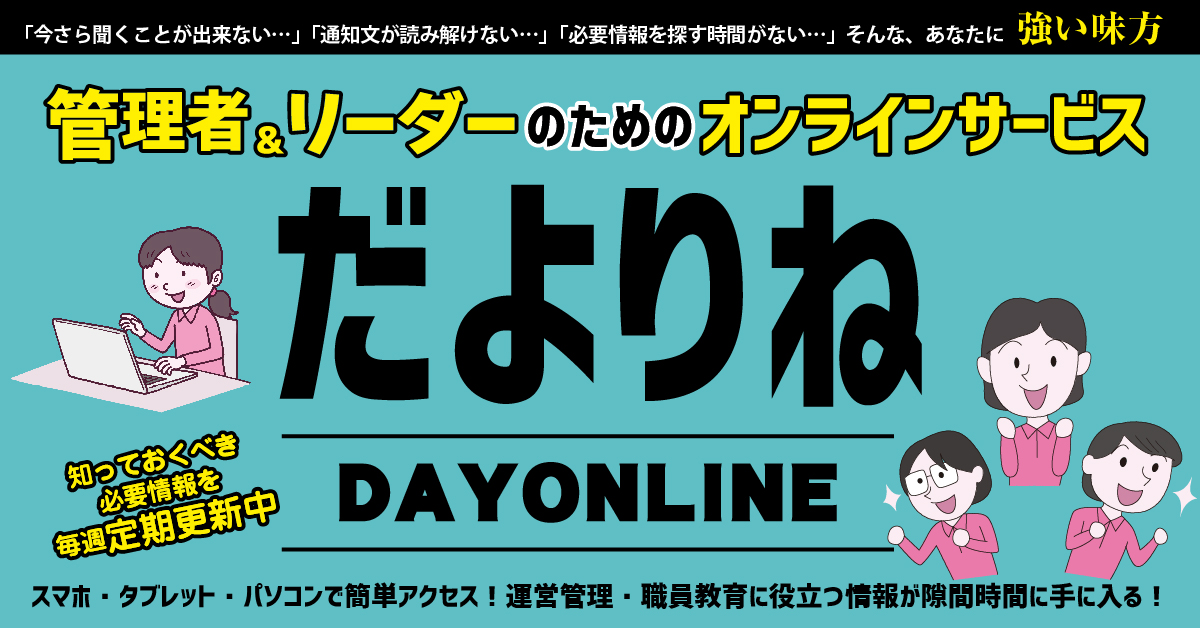【PR・営業ワンポイントアドバイス】デイサービス稼動率アップのための戦略
デイサービスで稼働率を上げることは、黒字経営する上での絶対条件です。
稼動率を簡単に言うと、営業時間を通して来て下さっているご利用者が定員中何人かをパーセントで出したもの。
例えば、営業時間9:15~16:30の7時間15分・定員18名のデイでは、1名7時間で通ってくれるだけでその日の稼動率は5.5%上がりますが、
午前・午後の半日利用のご利用者がそれぞれ1人ずついた場合、2名の利用でも稼働率は5.5%と7時間分しか上がりません。
こういった考え方の経営指標を稼働率と言います。
これを高めていくには、①利用者増 ②利用回数を増やしてもらう ③欠席・中止対策をする ④滞在時間を延ばす
これら④つの取り組みが重要となってきます。
今までの【PR・営業ワンポイントアドバイス】では、①についての情報は山ほど記事にしてお伝えしてきたと思いますので、
それ以外の要素についての解説と、戦略についてお伝えをしていきたいと思います。
ぜひ、貴事業所の稼動率UPに活用していただけると嬉しいです。
介護事業者の倒産は過去最大…2021年51件の倍の100件に
【対策は済みましたか?】電気代が高騰しています
2022年3月以降のウクライナ情勢の影響による石炭や液化天然ガス(LNG)等の輸入価格高騰の影響を受け、燃料費調整額が値上がりしています。
電気料金は「基本料金」と「電力量料金」から構成され、以下のような計算式で請求額が算出されています。
(基本料金単価×契約電力×(185-力率)/100)+(電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整額)+再生エネルギー発電促進賦課金
この燃料費調整額は、簡単に言うと「発電事業者を守るための」燃料調整制度に基づいて請求されている金額のことです。
日本はエネルギー資源をほとんど輸入で賄っているので、世界の経済状況や政局変化等が燃料価格に大きく影響するんですね。
もし、電気代に燃料調整額が無ければ発電事業者は、自分たちではどうしようもない環境因子の影響を受け、破綻してしまう可能性があるんです。
そうなると、私たちの生活にもはや必須の電気ですから困りますよね?これが今、大幅な値上がりをして個人や事業主にダメージを与えています。
すなわち、発電事業者もピンチということです。
2022年度9月時点の燃料費調整額は、中国電力で約9.0円でした。
5,000KWh/月の使用電力量がある事業所だと45,000円の電気代負担増。
来月は11.0円が予測されており、私は3月末15円を予測しています。上記の使用電力量がある事業所では、10月以降の半年間だけで約40万円の負担増です。
これは非常に・・・厳しいですよね。
さらに電力量料金単価を値上げしたり、法人の新規申込を遮断している業者も増えてきましたので、異常事態性を早くキャッチして対策を講じていきましょう。
【対策案】
① ダメ元で、民間事業者への切り替えを進める(電力量単価を安くすることにこだわる)
② 節電(使用電力量を落としていく)➔ ご利用者に影響の出ない範囲内で
② 入居施設等で共益費用をいただける場合は値上げの実施
広島県の銭湯入浴料480円に…11月1日より30円値上げ
広島県は2022年11月1日より銭湯入浴料の上限を大人(12歳以上)で30円値上げし、480円にする。
原油価格や電気代の高騰への対応としています。
他地域の価格例は以下の通りです。
・北海道:480円
・東京:500円
・千葉:480円
・神奈川:500円
・埼玉:480円
・京都:490円
【傍聴報告】第99回介護保険部会「人材確保と生産性向上」
2022年10月17日(月)に、第99回介護保険部会が開催されましたので月刊デイ編集長であり日本通所ケア研究会会長の立場から私感を交え報告します。
今回の介護保険部会のテーマは「人材確保と生産性向上」で、具体的な検討項目は以下の通りです。
【1】総合的な介護人材確保
(1)多様な人材の更なる参入に向けて、どのような方策が考えられるか
(2)介護福祉士を介護職グループリーダーとして育成するための方策
(3)多様な年齢層・多業種に向け、介護の魅力・関心を持ってもらうための効果的な情報発信
(4)外国人介護人材への方策
【2】地域における生産性向上の推進体制の整備
(1)介護の生産性向上に関する地方公共団体への方策・法令での役割明確化
(2)施設・在宅でのテクノロジーの活用・普及
(3)介護助手の確保・方策
(4)経営の大規模化・協働化、連携推進法人の普及・活用、管理者等のテレワークなど
【PR・営業ワンポイントアドバイス】ケアマネ営業の悩みについて解説
稼動率を上げるために「ケアマネへの営業」を実施するように上長から指示を受けた皆さん。
「どうすれば良いのか分からないよ~」と不安になっていませんか?
・営業なんてしたことない
・営業とかが嫌いで介護業界に入ったのに!!!
・ご利用者を増やすために売り込むなんて公的じゃない
・ケアマネさんも忙しいと思うし行き辛い
このように思ってしまう方、多いのではないでしょうか?
今回の記事では、上記のような皆さんの不安や悩みが解決される内容になっています。
また、記事内容を参考に実践するだけで、重くのしかかっていた「ケアマネ営業」が楽勝!!に思えてくると思いますので、ぜひ、参考にしていただければ嬉しいです。
【個別機能訓練加算】ケアの流れの中での整合性と計画書の中での整合性
ケアの流れの中での整合性
ケアの流れで大切とされているのは、アセスメントとアセスメントに基づく計画作成、計画に基づく実施です。
厚生労働省通知では、以下の通り定められています。
人出不足増
日本商工会議所が全国の中小企業を対象とした人手不足に関する調査で、人手が不足していると答える企業が増加していることが分かりました。
業種別では
(1)建設…77.6%
(2)運輸…76.6%
(3)介護・看護…74.5%
(4)宿泊・飲食…73.9%
(5)情報…71.6%
となっています。
紙の保険証2024年秋に廃止…マイナンバーカードと一体化を検討
政府が紙の健康保険証を2024年秋にも廃止し、マイナンバーカードと一体化した保険証の利用への切り替えを検討しています。
政府関係者は、「マイナンバーカードをどうしても持ちたくない人が、医療を受けられない状況をつくらないように配慮しながら進めなければならない」と語っています。
【PR・営業ワンポイントアドバイス】ヒアリングのコツについて
新規利用者を獲得するために、電話をしたり営業を仕掛けたりされていると思いますが、直接的な利用がきちんと生まれていますか?
期待通りの数字が挙げられていない・・・と悩んでいる方向けに今回は「ヒアリングのコツ」について記事を書かせていただきました。
営業やTELには以下の流れがあります。
①自己紹介
②導入
③ヒアリング~本題
④クロージング
この中でも最重要なのが、「③ヒアリング~本題」部分です。
ここで、相手の課題を抽出してサービスの必要性に気付いてもらえなければ、商品やサービスは売れません。
しかし、相手は「現在の課題を課題とも認識できていない」ものです。
どのようにすれば、課題点に気付き、サービスの重要性に気付いてもらえるのか、「ヒアリングのコツ」について説明していきます。