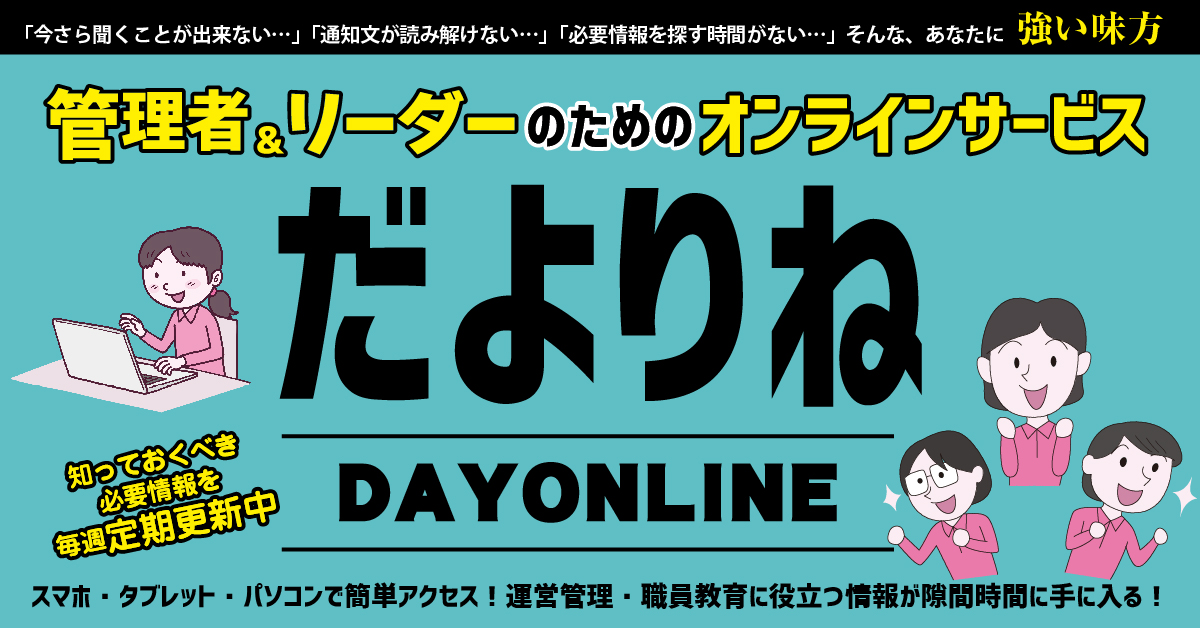【傍聴報告】第103回介護保険部会「全世代型社会保障構築会議について(報告)・給付と負担について」
2022年11月28日(月)に「第103回介護保険部会」が開催されましたので、月刊デイ編集長であり日本通所ケア研究会会長の立場から私感を交え報告します。
今回の介護保険部会のテーマは「全世代型社会保障構築会議について(報告)」と「給付と負担について」でした。
議論のテーマは「給付と負担について」で以下の7つについて2巡目の議論となりました。
【1】被保険者範囲・受給権者範囲
【2】補足給付に関する給付の在り方
【3】多床室の室料負担
【4】ケアマネジメントに関する給付の在り方
【5】軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
【6】「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準
【7】高所得者の1号保険料の負担の在り方
【PR・営業ワンポイントアドバイス】USJから学ぶV字回復術
2001年に華々しく開業したものの、開業前半苦境が続いたUSJの復活には学ぶものが沢山あります。
2010年に森岡氏(現:株式会社刀 代表取締役)が入社した時点で750万人程度だった入場者数は、2016年度には1,390万人を超えました。
この成功の秘訣について盛岡氏は著書「USJを劇的に変えた、たった1つの考え方」で語っています。
その1つとは何でしょうか?皆さんはすぐに答えられますか?
貴事業所の稼動率をアップさせるために必要な「1つ要素」は何だと思いますか?
今回の記事では、この「1つの要素」をはじめとする森岡氏の取り組みを、介護事業所運営に当てはめながら、
貴事業所の稼動率上昇に欠かせないエッセンスについて、ご紹介させていただければと思います。
貴事業所の稼動率上昇のキッカケとなれば嬉しく思います。
【傍聴報告】第102回介護保険部会「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について」
2022年11月24日(木)に「第102回介護保険部会」が開催されましたので、月刊デイ編集長であり日本通所ケア研究会会長の立場から私感を交え報告します。
今回の介護保険部会のテーマは前回101回と同様で「地域包括ケアシステムの深化・推進について」で、具体的な検討項目は以下の通りです。
【1】総合事業の多様なサービスの在り方、通いの場、一般介護予防事業
【2】地域包括支援センターの体制整備等
【3】保険者支援、機能強化交付金、給付適正化、地域差分析
【4】要介護認定
※今後の介護保険部会の流れは2022年11月28日(月)「給付と負担について」、12月上旬に「取りまとめに向けた議論」が予定されています。
施設に入所させるのは「かわいそう」を払拭・一掃する
【スタッフマネジメント】自分の判断で勝手に残業する職員
【事例】
複数のデイサービスを経営しているA法人は、「原則残業禁止」という取り組みを行っています。
しかし、「残業禁止」を周知して記録ソフトを導入したり、事務職を採用するなどの業務の効率化を図っているにもかかわらず、数名の残業時間が減りません。
残業時間が増えている人もいるようです。
どうしたらよいでしょうか?
【PR・営業ワンポイントアドバイス】自分や施設を売り込めていますか?
【スタッフマネジメント】残業を拒否する職員
【事例】
Aデイサービスは人手不足で、毎日数名に残業をお願いしないと業務が回らない状況です。
しかし入職3年目の職員Bに声を掛けると、
「この後、友人と約束があるのでできません。ほかの方にお願いできませんか?」
といつも断られてしまいます。
ほかの職員からは「なぜBさんだけいつも残業しないのか?」と不満の声が上がっています。
【傍聴報告】第101回介護保険部会「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について」
2022年11月14日(月)に「第101回介護保険部会」が開催されましたので、月刊デイ編集長であり日本通所ケア研究会会長の立場から私感を交え報告します。
今回の介護保険部会のテーマは「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について」で、具体的な検討項目は以下の通りです。
【生活を支える介護サービス基盤の整備】
■地域の実情に応じた介護サービスの基盤整備
■在宅サービスの基盤整備
■ケアマネジメントの質の向上
■在宅医療・介護連携
■地域における高齢者リハビリテーションの推進
■施設入所者への医療提供
■施設サービス等の基盤整備
■住まいと生活の一体的支援
■介護情報利活用の推進
■科学的介護の推進
■財務状況等の見える化
■介護現場の安全性の確保、リスクマネジメント
■高齢者虐待防止の推進
【PR・営業ワンポイントアドバイス】おすすめのサービスを紹介します
【PR・営業ワンポイントアドバイス】効率的に仕事を進めるための方法