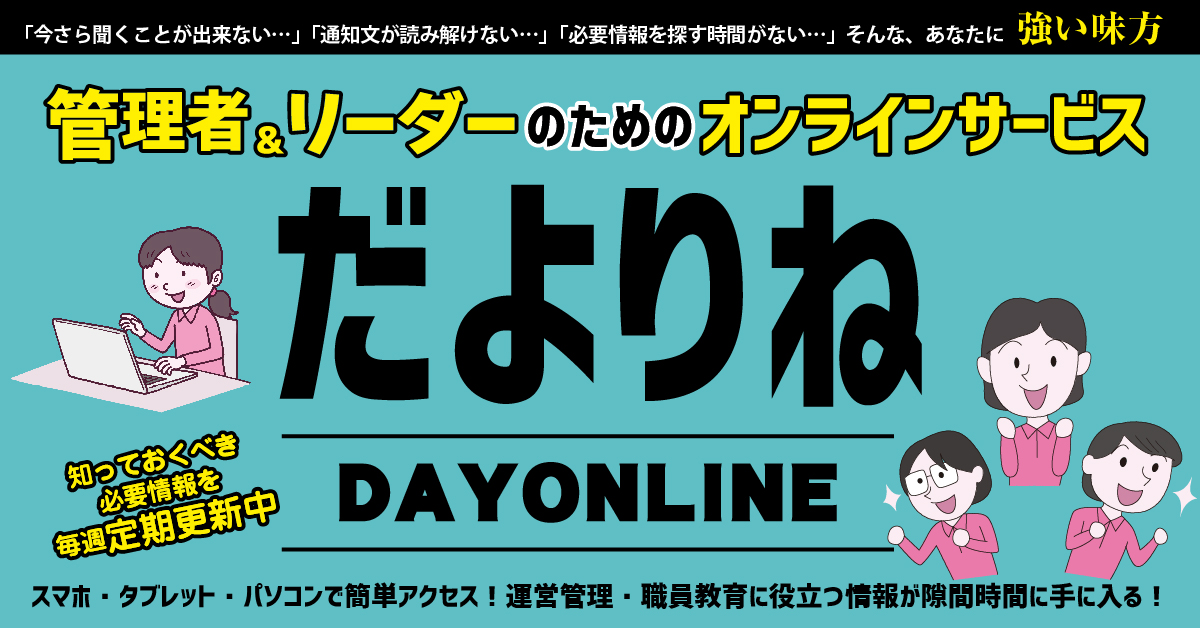【PR・営業ワンポイントアドバイス】営業で成果を出している人の「考え方」から学ぼう
営業・広報への向き合い方、すなわちメンタリティの領域はHow toと同じくらい大切です。
介護業界でも、営業・広報活動の重要性が高まってきていることから、慣れない営業活動にどう向き合ったら良いのか悩んでいる介護職員の方も多いのではないでしょうか?
今回は、そんな皆さまのメンタリティを強化すべく、他分野も含めたトップセールス(営業会社で上位3位以内)が日頃から何を考えて行動しているかを共有したいと思います。
介護でも建設でも医療でも「営業」は同じです。業界や取り扱うものが違っても売れる人は売れるのです。
では、なぜ売れてしまうのか・・・その答えも今回の記事で分かっていただけると思います。
運営基準に関するQ&A【食費の設定・取り扱い/理美容サービスの利用の取り扱い】
【Q】
食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。
また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
【A】
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。
特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。 利用者負担第4段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者負担第1段階から第3段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
具体的には、例えば、朝食400円、昼食450円、夕食530円と設定した場合、利用者負担第3段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650円であるので、朝食のみ(400円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200円が補足給付として支給される。
24.3.30事務連絡 介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日)」
運営基準に関するQ&A【その他の日常生活費の取り扱い】
【問1】
個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」とは、どういったものが想定されるのか。
【答】
歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者(又は施設)が提供するもの等が想定される。
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 その他の日常生活費に係るQ&Aについて
【PR・営業ワンポイントアドバイス】コミュニケーションにおける知っておくと得するノウハウ5選
営業に限らず、日々ご利用者やご家族・ケアマネとコミュニケーションをとっている介護職員の皆さまは「コミュニケーションのプロ」だと思うのですが、
コミュニケーションを取るのがが苦手な方や、提案が必要な場面でなかなかYESを取れないとお悩みの方に役立つ情報をお届けします。
言い回しや、あるポイントを気を付けるだけで「伝わり方」であったり、「YESの取りやすさ」は変わってきます。
今回の記事では、得するコミュニケーションノウハウについて会員様限定で5つだけお伝えいたします!
ぜひ、貴事業所のコミュニケーション向上のキッカケとして本記事をご活用いただければ幸いです。
【デイで必要な人員基準・要件の理解】常勤換算の計算方法とポイント
なぜ常勤換算が必要なのか?
デイサービスには人員基準が設けられていますが、人員基準を満たしているかどうかを「常勤換算」で計算します。
常勤換算は、その事業所で働いている人の平均人数を表します。
では、なぜこのような計算が必要になるのでしょうか。
デイサービスで働いている人には、正社員やパート職員がおり、それぞれ労働時間が異なる人を1人として数えると人員基準を満たさない場合が発生し得ることから、同一の基準で労働者の平均を表すために、常勤換算の計算が必要となるのです。
常勤換算は1ヶ月(4週間)を基本として計算します。
【サービスの質向上】認知症高齢者の転倒に関係の深い各種機能とトレーニング
認知症高齢者の転倒予防を進める上で、バランスを保ったり、骨折を防いだりする心身のメカニズムを知ることが大切です。
転倒・骨折予防に関係の深い機能トレーニング法について紹介します。
<認知症高齢者の転倒・骨折予防に関係の深い機能>
【1】筋力
【2】バランス
【3】姿勢反射・姿勢反応
【4】保護伸展反射
【5】注意機能
【6】身体認知・自己身体能力認知 ほか
【傍聴報告】第96回介護保険部会「地域包括ケアの更なる深化・推進(1)」
2022年8月25日(木)に、第96回介護保険部会が開催されましたので月刊デイ編集長であり日本通所ケア研究会会長の立場から私感を交え報告します。
今回の介護保険部会のテーマは「地域包括ケアの更なる深化・推進(1)」で、具体的な検討項目は以下の通りです。
【1】在宅サービスの基盤整備
【2】在宅医療・介護連携
【3】施設サービスの基盤整備
【4】施設入所者に対する医療提供
【5】ケアマネジメントの質の向上
【6】科学的介護の推進
【7】地域における高齢者リハビリテーションの推進
【8】住まいと生活の一体的支援
【サービスの質向上】モンスター家族・困った利用者への対応の基本原則
家族・利用者のモンスター化が増えている
近年、増加傾向にあるクレーマーのモンスター化という問題について、デイサービス職員としても何らかの対応が求められています。
モンスター化したクレーマー対応以前に、そもそもの対応の基本原則の再確認をしたいと思います。
基本原則がしっかり定着していない事業所は、モンスター化したクレーマーには到底太刀打ちできません。
基本原則をしっかりと理解・実践できる事業所運営を目指していきましょう。
【サービスの質向上】転倒予防の視点
転倒予防の視点(1)-段階別アプローチ-
高齢者は、転倒→骨折→生活機能低下という流れを引き起こす危険性が高く、転倒予防のためには、これらの流れを断つことが重要です。
まず
(1)転倒しにくい心身・環境づくり
(2)骨折しにくい心身・環境づくり
(3)生活機能が低下しにくい心身・環境づくり
の視点で転倒予防について考えていきましょう。
【PR・営業ワンポイントアドバイス】アポイントを取る時のコツ
普段、自事業所の営業活動を行う中でアポイントを取る機会ってそうないと思います。
既に利用して下さっているケアマネさんへの報告書提出と合わせて営業をかけるであったり、新規のケアマネ事業所でもアポを取らず飛び込みでいかれる方が多いと思います。
ケアマネさんは事業所に悪い顔は出来ないので、壁もあまりないと思いますしね。
ただ、病院となると話は変わってきます。
地域連携室の職員は、日々退院調整や生活相談の問合せでバタバタとしていますし、直接的な関係性も薄い介護事業所に対して快く対応して下さるとは限りません。
わざわざ病院に行っても不在や多忙を理由にまとまった時間を取ってもらえなかったり、不快に思われることもあります。
結論、病院に営業に行く際は必ず「アポ」を取った方が良いです。
ただ、アポを取り慣れていない方が、相手を不快にさせることなく話を進めるにはどうすれば良いか分からず悩んでいる方もいると思います。
今回は、3人しか来る予定の無かった見学会に40人を集客したアポマスターの私が、ポイントについて分かりやすく解説をします。
アポ以外の場面でも使えるので、この記事が貴事業所の接遇力向上の力になれれば嬉しいです。