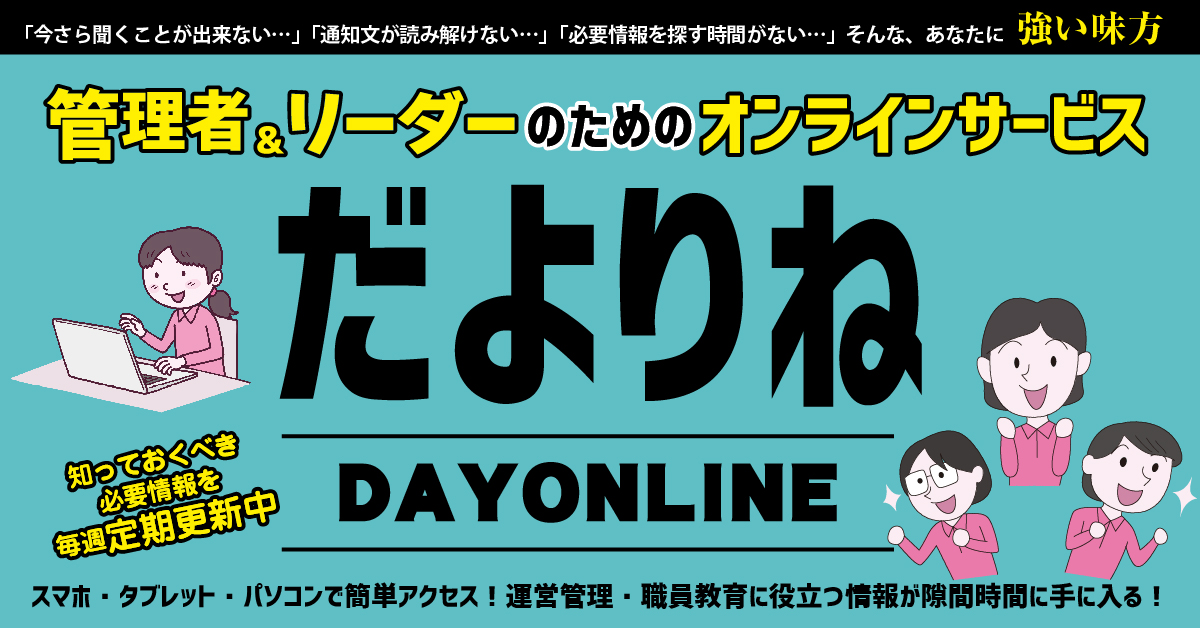虐待は論外!今こそ「不適切ケア」を見直す部内ミーティングを
2025.10.02
介護の使命は「利用者の尊厳を守り、QOL(生活の質・人生の質)を高めること」です。
しかし残念ながら全国では、虐待や不適切ケアが後を絶たず、現場全体の倫理観や安全管理が問われています。
この機会に、各部署で緊急ミーティングを実施し、自分たちのケアに不適切な行為やリスクが潜んでいないかを必ず確認しましょう。
【事例1】大阪・羽曳野市 老健施設での虐待事件
大阪府羽曳野市の介護老人保健施設「まほろば」では、職員3人が1年間にわたり23人の利用者を平手でたたく虐待行為を継続していました。
さらに、制止せずに笑って見ていた職員2人も「心理的虐待」に当たると判断されています。
発覚のきっかけは、医師が利用者の体にあざを見つけたことでした。
これは一人の職員の問題ではなく、職場全体の風土や監視機能の欠如が問われた事件です。
【事例2】入浴介助中の死亡事故(大阪市内)
大阪市の特別養護老人ホーム「アルカンシエル東成」では、70代の入所者が入浴介助中に高温の湯に入れられ、全身にやけどを負い死亡する事故が発生しました。
介助を担当していた介護福祉士(アルバイト職員)が逮捕されています。
入浴は「交通事故の約4倍の死亡リスク」がある極めて危険なケアです。
わずかな不注意や不慣れな対応が、利用者の命に直結することを改めて認識しなければなりません。
【広島県の統計】虐待発生状況(令和5年度)
広島県が公表した調査結果によると、県内でも虐待は依然として発生しています。
特に 家庭内虐待は相談件数・判断件数ともに増加しており、「どの地域でも他人事ではない」現実を示しています。
■施設内虐待
相談・通報件数:80件
虐待判断件数:51件(前年度34件 → 増加)
主な内容:身体的虐待、心理的虐待、介護放棄、経済的虐待
■家庭内虐待
相談・通報件数:894件(過去最多水準)
虐待判断件数:424件(前年度419件 → 増加)
被害者の特徴:75%が女性、82%が75歳以上、要介護・要支援認定者が80%、そのうち認知症のある人は96%
数字が示すのは、虐待が例外ではなく、地域・施設を問わず現場で起こり得る日常的なリスクであるという事実です。
入浴介助で守るべき「5つの鉄則」
入浴はもっともリスクの高いケアのひとつです。
以下の基本を必ず徹底しましょう。
忘れ物チェック:タオル・着替えなど事前準備を確実に
転倒防止:移動・洗体時は細心の注意を
水分補給:入浴前にしっかりと摂取、脱水や熱中症を防ぐ
湯温のダブルチェック:職員・本人双方で確認
絶対に目を離さない:浴槽内では一瞬の油断も許されない
部署で確認すべき「不適切ケアチェックポイント」
・感情的な対応や威圧的な言葉が出ていないか?
・職員同士で「見て見ぬふり」をしていないか?
・忙しさを理由に「雑なケア」になっていないか?
・入浴や食事など高リスク場面で、マニュアル通りの対応ができているか?
まとめと行動提案
虐待や事故は「一部の職員の問題」ではなく、組織全体の姿勢が問われる問題です。
今こそ部内で率直に意見交換を行い、現場の小さな「ひずみ」や「慣れ」を是正することが重要です。
行動提案
・今週中に部署ごとの緊急ミーティングを開催
・上記チェックポイントを題材に全員で再確認
・問題があれば即管理者に報告し、改善策を共有